「坪単価の平均を知れば、理想の家を建てることができる」
まずは、結論してこの事をお伝えしておきます。
とはいえ、
- 注文住宅の坪単価ってなに?
- 注文住宅の坪単価は平均どれくらい?
- 自分たちの理想の坪単価はいくらぐらい?
という疑問をお持ちではありませんか?
そこで、この記事では坪単価について分からないというお悩みを、
タマホームで注文住宅を建てた筆者の観点から解決します。
具体的には
- 坪単価の基礎知識がわかる
- 注文住宅の坪単価の全国平均がわかる
- 坪単価別の注文住宅の特徴
- 理想の坪単価のシミュレーション方法を紹介スト
の順番にご紹介していきます。
\ 間取り、資金計画で悩んでいる方必見!/
1.注文住宅の坪単価とは?1坪(約3.3m2)あたりの建築費のこと!
注文住宅は自分の好みやライフスタイルに合わせて家を建てることができる魅力的な選択肢ですが、その分費用も高くなりがちです。
では、注文住宅の坪単価はどのくらいなのでしょうか?
一概には言えませんが、土地の条件や建築会社の規模、設計や仕様、工法などによって大きく変わります。
そこで、この章では注文住宅の坪単価の基礎知識とハウスメーカーと工務店の坪単価について紹介します。
1-①.注文住宅の坪単価とは?
| 坪単価の計算式 |
| 建物の本体価格 ÷ 延床面積 = 坪単価 |
| 延べ床面積が100坪で建築費用が3000万円だった場合 |
| 3000万円÷100坪=30万円 |
注文住宅の坪単価とは、一般的に 建築費用を延べ床面積で割った金額 のことを指します。
例えば、延べ床面積が100坪で建築費用が3,000万円の場合、坪単価は「3,000万円 ÷ 100坪 = 30万円」となります。
この計算により、大まかな建築コストを把握できます。
しかし、坪単価はあくまで参考値であり、実際の費用はさまざまな要素によって変動します。
坪単価だけで建築費用を判断すると、思わぬ追加費用が発生する可能性がある ため、注意が必要です。
1-②.ハウスメーカーと工務店では坪単価が違う!
一般的に、ハウスメーカーの方が工務店よりも坪単価が高い と言われています。
その理由の一つは、大量生産や標準化によって一定のコストを抑える一方で、ブランド力やアフターサービスの充実により価格が上がる ことです。
また、大手ハウスメーカーは広告宣伝費やモデルハウスの運営費もかかるため、これらの費用が建築費用に反映されることになります。そのため、坪単価が高くなりやすい傾向があります。
1-②-1.ハウスメーカーの坪単価は約60万円!
ハウスメーカーの坪単価は、建築する家の規模や仕様、地域によって大きく異なります。
一般的には、坪単価が高いほど、家の品質や性能が高くなると考えられますが、必ずしもそうとは限りません。
ハウスメーカーによっても、坪単価の計算方法や含まれる項目が異なるため、単純に比較することはできません。
そこで、ハウスメーカーの坪単価について具体的な金額を知るためには、以下の3つのポイントに注意する必要があります。
- 1.坪単価に含まれる項目を確認する
- 2.同じ仕様で複数のハウスメーカーから見積もりを取る
- 3.実際に建てた人の口コミや評判を調べるト
これらのポイントを踏まえて、ハウスメーカーの坪単価の平均値を参考にしてみましょう。
全国平均では、ハウスメーカーの坪単価は約60万円と言われています。
しかし、これはあくまで目安であり、実際には40万円から100万円以上まで幅があります。また、地域によっても差があります。
例えば、関東地方では約65万円、関西地方では約55万円となっています。
1-②-2.工務店の坪単価は約40万円!
工務店の坪単価は、規模や実績、住宅の設計や仕様、地域や時期などによって大きく異なります。
一般的に、大手工務店やハウスメーカーの坪単価は30万円~40万円程度で、中小工務店の坪単価は20万円~30万円程度と言われています。
ただし、これはあくまで目安であり、実際には個々の条件によって異なります。
そのため、注文住宅を検討する際は、いくつかの工務店に見積もりを依頼し、具体的な費用を比較することが大切です。
また、工務店ごとに得意とする住宅のタイプも異なるため、自分の希望に合った会社を選ぶことが重要です。
>>注文住宅の坪単価を徹底比較!ハウスメーカーと工務店の坪単価の一覧表と坪単価を抑える方法を紹介
2.注文住宅の坪単価の全国平均は約100万円!
注文住宅の坪単価とは、建築費用を建物の床面積で割ったものです。
つまり、1坪あたりにかかる費用のことです。
注文住宅の坪単価は、建物の規模やデザイン、仕様や設備、地域や工務店などによって大きく変わります。
そのため、一概に全国平均を出すことは難しいのですが、参考までに紹介していきます。
2-①.注文住宅の坪単価の全国平均
注文住宅の坪単価とは、建築費用を敷地面積で割ったもので、土地や建物の規模や仕様によって異なります。
全国平均は約100万円と言われていますが、これはあくまで目安であり、地域や業者によって大きく変動します。
2-②.【建物のみ】坪単価の平均は20~60万円
建物のみの坪単価とは、敷地や外構を除いた建物本体の工事費用を坪(約3.3㎡)あたりで表したものです。
一般的に、木造住宅は20~30万円、鉄骨造や鉄筋コンクリート造は40~60万円程度が相場とされています。
ただし、これは目安であり、実際の費用は建物の形や階数、間取り、窓の数などによって変動します。
例えば、立地条件が良い場合、採光や通風を考慮して窓を多く設けると、その分コストが増えます。
また、複雑な形状や高さのある建物は、構造計算や耐震性能にも影響します。
そのため、自分の希望や予算に応じて、どこにコストをかけるかを慎重に考えることが重要です。
2-③.【土地+建物】坪単価の平均は90~110万円
土地の坪単価は地域によって異なりますが、全国平均は約30万円とされています。
一方、建物の坪単価は建築会社や設計内容によって変動し、一般的には約60万円~80万円程度が相場です。
そのため、土地+建物の坪単価の平均は約90万円~110万円となります。
ただし、これはあくまで目安であり、都心部や人気エリアでは土地の坪単価が高く、高級な素材や設備、複雑なデザインを採用すると建物の坪単価も上昇します。
逆に、郊外では土地の坪単価が安く、シンプルなプランやDIYを取り入れることで建物のコストを抑えることが可能です。
注文住宅を建てる際は、予算に合わせて土地と建物のバランスを考えることが重要です。
3.【坪単価別】注文住宅の特徴
坪単価は、土地や建物の規模、設備や仕様、工法や工務店などによって大きく変わります。
一般的には、坪単価が高いほど高品質で高性能な注文住宅になりますが、必ずしもそうとは限りません。
そこで、坪単価別に注文住宅の特徴を見ていきましょう。
3-①.坪単価30-50万円の注文住宅




引用:【SUUMO】 【本体価格1130万円/30坪台/間取図有】北欧デザイン×シンプルモダン。予算内で理想がカタチに – ジブンハウス の建築実例詳細 | 注文住宅
坪単価30~50万円の注文住宅は、ローコスト住宅に分類されます。
自由に間取りを設計する家づくりというよりは、既に決められた規格に基づいて建築する規格住宅を展開している会社が多いです。
家の特徴としては、片流れ屋根が採用されているのが多く、間取りは1階と2階の面積が同じ総二階建ての注文住宅になっています。
間取りをこだわらなければ、システムキッチンやお風呂なども標準仕様になります。
30~50万円以下の坪単価の注文住宅は、予算が限られている方やシンプルな暮らしを求める方に向いています。
この坪単価帯では、土地や建物の面積を小さく抑えたり、標準仕様の素材や設備を選んだりすることでコストを抑える必要があります。
また、建築家や工務店の選択肢も限られるため、自分で調べたり相談したりする能力が求められます。
この坪単価帯の注文住宅の特徴は、無駄のないシンプルなデザインや間取りであることや、省エネやエコなど環境に配慮した工法や設備を採用していることです。
3-②.坪単価50-70万円の注文住宅






引用:【SUUMO】 【東近江市/2000万円台/空気がきれい】床下エアコン1台で家じゅう快適な温度、安心して子育てできる家 – マコトホーム 彦根店の建築実例詳細 | 注文住宅
坪単価50~70万円の注文住宅は、ローコストメーカーやミドルコストで建てられる会社が多いです。
ローコストメーカーだと、自由設計の家づくりが可能になってきます。
ローコスト住宅よりは、間取りの自由度も高くなってくるので、希望を叶えられる部分も多くなってきますよ。
建物の形状も基本総二階が多いですが、角が多く複雑な形状のデザインの注文住宅にすることもできるようになります。
また、大手ハウスメーカーの中では、低いグレードのシリーズがこの価格帯に当てはまりやすいです。
坪単価50~70万円の注文住宅は、一般的な注文住宅の相場です。
この坪単価帯では、土地や建物の面積は平均的であることが多く、標準仕様から一部カスタマイズした素材や設備を選ぶことができますよ。
また、建築家や工務店も多数ありますので、自分の好みや予算に合ったプロを探すことができます。
この坪単価帯の注文住宅の特徴は、バランスの良いデザインや間取りであることや、快適さや機能性を重視した工法や設備を採用しています。
3-③.坪単価70-100万円の注文住宅






引用:【SUUMO】 【ガレージ/バルコニー/変形地】両面開口で、眺望や光と風の心地よさを楽しむ「四季を感じる家」 – オカケン の建築実例詳細 | 注文住宅
大手ハウスメーカーでは、坪単価70~80万円で商品を展開しています。
住宅の種類としては、木造系だけでなく、鉄骨系も選択肢にすることができます。
このレベルの高級住宅メーカーになると、使用する素材が最上級のものだったり、設計の自由度が極めて高いです。
そのため、自分の理想の家づくりを実現しやすくなります。
また、建てた後のアフターフォローが充実しているので安心感があります。
坪単価70-100万円の注文住宅は、高級感や個性を求める方に向いています。
この坪単価帯では、土地や建物の面積は広く、オーダーメイドの素材や設備を選ぶことができます。
また、建築家や工務店も一流のプロが多く、自分の理想を実現することができますよ。
この坪単価帯の注文住宅の特徴は、高品質なデザインや間取りであることや、最新の技術や設備を採用しています。
>>【注文住宅の坪単価】工務店とハウスメーカーの平均坪単価を徹底比較!費用を抑えるコツも紹介
4.理想の坪単価のシミュレーション方法
坪単価は様々な要素によって変動するため、一概に決めることはできません。
では、どうやって自分の理想の坪単価を見つけることができるのでしょうか?
そのためには、シミュレーションが必要になってきます。
シミュレーションとは、自分の希望する住宅の条件や仕様を設定して、それに応じた坪単価を計算することでおおよその坪単価を把握することができます。
シミュレーションを行うことで、自分の理想の住宅がどれくらいの費用になるか、また、どのような要素が坪単価に影響を与えるかを知ることができます。
シミュレーションを行う方法はいくつかありますが、今回は、インターネット上で利用できる無料のサービスを紹介していきます。
4-①.費用シミュレーションをする前に確認すること
注文住宅を建てるとき、費用はどのくらいかかるのでしょうか?
費用シミュレーションをすることで、予算やローンの計画を立てやすくなります。
しかし、費用シミュレーションをする前に、いくつかのことを確認しておく必要があります。
そうしないと、実際の費用と大きくずれてしまう可能性があります。
この章では、注文住宅の費用シミュレーションをする前に確認するべきことについて紹介していきます。
4-①-1.建てたい家の費用を把握する
家の費用を知る方法は大きく分けて2つあります。
1つ目は、ハウスメーカーや工務店に相談する方法です。
自分の希望するプランや仕様を伝え、見積もりを出してもらえます。
メリットは、イメージに近い家の費用がわかることですが、時間や手間がかかる点がデメリットです。
2つ目は、インターネットで調べる方法です。
ハウスメーカーや工務店のホームページやブログで、過去の事例や価格を確認できます。
手軽に多くの情報を得られるのがメリットですが、自分の希望する条件と完全に一致する例がない可能性があります。
それぞれの方法の特性を理解し、状況に応じて活用するとよいでしょう。
>>【一覧表つき】注文住宅の費用は大きく分けて3つ!内訳や筆者の費用内訳も公開
4-①-2.自己資金をいくら準備できるのか確認
注文住宅は自分の好みやライフスタイルに合わせて設計できるメリットがありますが、その分費用も高くなります。
そこで、自己資金をいくら用意する必要があるのか、事前に把握しておくことが大切です。
自己資金とは、住宅ローン以外に自分で用意するお金のことです。
一般的には、土地代や建築費の10%以上が目安とされています。
しかし、これはあくまで目安であり、実際には個人の収入や支出、家族構成などによって変わります。
そこで、自己資金を確認するには以下の3つのステップを踏むことをおすすめします。
これが自己資金の基本となります。貯金額は定期預金や投資信託なども含めて計算しましょう。
これが自己資金の増減に影響します。
収入は給与やボーナスなどを合計し、支出は生活費やローン返済などを引き算します。
収入から支出を引いた残りが毎月の貯蓄額です。
この貯蓄額を将来の建築予定時期まで積み上げると、自己資金の増加分がわかります。
これが自己資金の必要額です。
見積もりは複数の業者から取ることで、相場や適正価格を把握できます。
見積もりには土地代や建築費だけでなく、諸経費や税金なども含まれていることに注意しましょう。
以上の3つのステップで、自己資金をいくら準備できるか、そしていくら必要かがわかります。
自己資金が足りない場合は、住宅ローンの借入額を増やすか、注文住宅の規模や仕様を見直すかのどちらかを検討する必要があります。
逆に自己資金が余る場合は、住宅ローンの借入額を減らすか、注文住宅のグレードアップやオプション追加などを考えることができます。
自己資金は注文住宅を建てる上で重要な要素です。
しっかりと確認しておくことで、無理なく快適な住まいづくりができますよ。
4-①-3.月々のローン返済額はいくらまで大丈夫なのか
注文住宅を建てるのは一生に一度の大きな買い物です。
ローンを組む際は、将来の収入や支出を考え、無理のない返済計画を立てることが重要です。
一般的に、月々のローン返済額は家計収入の25%以下に抑えるのが目安とされています。
例えば、家計収入が50万円なら、返済額は12万5000円以下が理想です。
具体的な借入金額を知るには、住宅ローンシミュレーターを活用すると便利です。例えば、月々12万5000円の返済で、金利1.5%、返済期間35年の場合、借入額は約3000万円になります。
ローンを組む際は、金融機関と相談し、将来の変動にも対応できる計画を立てることが大切です。夢を実現するために、慎重に準備を進めましょう。
4-①-4.土地と建物の購入割合を決める
注文住宅を建てる際に、土地と建物の購入割合を上手に決めることが重要です。
一般的には、土地と建物の費用はそれぞれ総予算の40~50%を目安にすると良いと言われています。
しかし、これはあくまで目安であり、自分の希望や条件によって変わってきます。
例えば、都心部や人気エリアでは土地の価格が高く、建物の費用を抑える必要があります。
逆に、郊外や田舎では土地の価格が安く、建物の費用を多めに見積もることができます。また、将来的にリフォームや増築を考えている場合は、建物の費用を少なめにしておくと余裕ができます。
土地と建物の購入割合を決める際には、以下のポイントを参考にしてください。
- 土地の価格や立地条件を調べる
- 建物の設計や仕様を決める
- 総予算やローンの返済能力を考慮する
- 将来的なリフォームや増築の可能性を考える
注文住宅は自分だけのオリジナルな家です。
土地と建物の購入割合を上手に決めて、理想の家づくりをしていきましょう。
4-①-5.注文住宅の費用の内訳を把握しておく
注文住宅を建てるときには、費用の内訳をしっかりと把握しておくことが大切です。
なぜなら、費用の内訳によって、自分の希望や予算に合ったプランを選ぶことができるからです。
また、費用の内訳を知っておくことで、工務店や設計事務所との交渉や契約もスムーズに進めることができます。
では、注文住宅の費用の内訳とはどのようなものでしょうか。
一般的に、注文住宅の費用は以下のように分類されます。
- 土地代
- 建物本体工事費
- 諸経費
- 付帯工事費
それぞれの項目について詳しく見ていきましょう。
土地代は、注文住宅を建てるために必要な土地の価格です。
土地代は、土地の広さや立地条件、周辺環境などによって大きく変わります。
土地代は、注文住宅の費用の中でも最も高額な部分であることが多いので、予算に合わせて適切な土地を選ぶことが重要です。
建物本体工事費は、注文住宅の建物そのものを建てるために必要な工事費です。
建物本体工事費は、建物の規模や構造、仕様、デザインなどによって変わります。
建物本体工事費は、注文住宅の費用の中でも最も自由度が高い部分であることが多いので、自分の希望やライフスタイルに合わせてプランニングすることが楽しいです。
諸経費は、注文住宅を建てるために必要なその他の費用です。
諸経費には、以下のようなものが含まれます。
- 設計料
- 監理料
- 保証料
- 融資手数料
- 登記費用
- 税金
諸経費は、注文住宅の費用の中でも最も見落としがちな部分であることが多いので、事前に確認しておくことが大切です。
付帯工事費は、注文住宅の建物以外に必要な工事費です。
付帯工事費には、以下のようなものが含まれます。
- 水道・下水・電気・ガスなどの引き込み工事
- 敷地造成工事
- 外構工事
- エアコン・カーテン・照明器具などの設備工事
付帯工事費は、注文住宅の完成度や快適性に大きく影響する部分であることが多いので、細かく見積もりを取っておくことがおすすめです。
以上が、注文住宅の費用の内訳についての説明です。
注文住宅を建てるときには、これらの費用の内訳を把握しておくことで、自分にとって最適な注文住宅を実現することができますよ。
4-②.【間取り別】注文住宅の費用シミュレーション例
注文住宅を建てるときに気になるのが、やはり費用ですよね。
どれくらいの予算が必要なのか、どんな間取りや設備が選べるのか、などなど。
しかし、注文住宅の費用は一概には言えません。建築地や土地の広さ、建物の規模やデザイン、素材や仕様、工法や施工会社など、さまざまな要素によって変わってきます。
そこで、この章では注文住宅の費用をシミュレーションする方法と間取り別の費用例をご紹介します。
これから注文住宅を検討されている方は、ぜひ参考にしてください。
4-②-1.平屋の費用シミュレーション例
まず、平屋の注文住宅の費用は、土地代、建物代、外構費などに分けられます。
土地代は、立地や面積によって大きく変わりますが、ここでは100坪(330平米)の土地を5000万円で購入したと仮定します。
建物代は、建築会社やプランによっても異なりますが、ここでは木造軸組工法で100平米の平屋を建てたと仮定します。
一般的に、平屋は二階建てよりも工事が簡単であるため、坪単価は安くなります。
ここでは坪単価30万円として、建物代は3000万円とします。
外構費は、駐車場や庭などを整備する費用ですが、ここでは500万円とします。
以上の仮定に基づいて、平屋の注文住宅の費用シミュレーション例は以下のようになります。
| 項目 | 費用(万円) |
|---|---|
| 土地代 | 5000万円 |
| 建物代 | 3000万円 |
| 外構費 | 500万円 |
| 合計 | 8500万円 |
もちろん、これはあくまで一例であり、実際には様々な要素によって費用は変動します。
例えば、土地の形状や条件、建物のデザインや仕様、外構の規模や素材などです。
また、諸経費や税金も考慮する必要があります。
したがって、平屋の注文住宅を建てる際には、自分の希望や予算に合わせて、複数の建築会社から見積もりを取って比較することが大切ですよ。
4-②-2. 3LDKの費用シミュレーション例
次は、3LDKの費用シミュレーション例をご紹介します。
もちろん、注文住宅の費用は家づくりの内容によって大きく変わりますが、参考にしてみてください。
まず、注文住宅の費用は大きく分けて以下の3つに分かれます。
- 土地代
- 建物代
- 諸経費
土地代は、建てる場所によって異なりますが、一般的には都心部や駅近などの立地条件が良いほど高くなります。
また、土地の形や勾配、道路幅なども影響します。
建物代は、建物の規模や構造、仕様、設備などによって変わります。
一般的には木造や軽量鉄骨よりも鉄筋コンクリートや鉄骨造のほうが高くなります。
また、デザインや間取り、素材や設備のグレードなども費用に反映されます。
諸経費は、建築確認申請や登記費用、保険料、税金などの手数料や諸費用です。
これらは建物代の10~15%程度と考えると良いでしょう。
では、具体的に3LDKの注文住宅の費用シミュレーション例を見てみましょう。
以下の条件で計算してみました。
- 土地面積:100㎡(30坪)
- 建物面積:90㎡(27坪)
- 建物構造:木造
- 建物仕様:中間グレード
- 設備仕様:中間グレード
- 間取り:1階:LDK(約20帖)、和室(約6帖)、トイレ・洗面所・浴室、2階:洋室×3(約6帖×3)、トイレ・洗面所
- 立地条件:郊外の一般的な住宅街
この場合の費用シミュレーション例は以下の通りです。
| 項目 | 費用(万円) |
|---|---|
| 土地代 | 2000万円(1坪あたり66万円) |
| 建物代 | 3000万円(1坪あたり111万円) |
| 外構費 | 450万円(建物代の15%) |
| 合計 | 5450万円 |
以上が、注文住宅の3LDKの費用シミュレーション例です。
この例では、土地代と建物代がそれぞれ合計費用の約4割ずつを占めています。
諸経費も忘れずに計算に入れることが大切です。
また、この例はあくまで一例であり、実際にはさまざまな要因で費用は変動します。
自分たちがどんな家を建てたいか、どんなライフスタイルを送りたいか、などを考えながら、自分たちに合った予算を立てることが大切ですよ。
4-②-3. 4LDKの費用シミュレーション例
4LDKの注文住宅を建てる際の費用シミュレーションを紹介します。実際の費用は土地や建物の仕様などによって変動しますが、参考にしてください。
まず、東京都内で100㎡(約30坪)の土地を1㎡あたり50万円で購入すると、土地代は5000万円になります。
次に、建物代ですが、木造軸組工法で150㎡(約45坪)の4LDKを建てた場合、1㎡あたり30万円と仮定すると、建物代は4500万円です。
さらに、設計料や登記費用などの諸経費は建物代の約12%とし、540万円程度と見積もられます。
これらを合計すると、土地+建物+諸経費で1億40万円となります。実際の費用は地域や仕様により異なるため、慎重に検討しましょう。
注文住宅の4LDKの費用シミュレーション例は以下のようになります。
| 項目 | 費用(万円) |
|---|---|
| 土地代 | 5000万円 |
| 建物代 | 4500万円 |
| 外構費 | 540万円 |
| 合計 | 10040万円 |
このように、注文住宅の4LDKの費用シミュレーション例では約1億円かかるということが分かりました。
しかし、これはあくまで一例であり、実際にはさまざまな要素によって変動します。自分の希望や予算に合わせてプランニングすることが大切です。
注文住宅を建てる際は、信頼できる業者と相談しながら進めていきましょう。
4-③.費用シミュレーションのおすすめ無料ツール
費用シミュレーションは、将来の収入や支出を予測し、資産形成やライフプランの見直しに役立つ方法です。
しかし、自分で行うには手間がかかり、正確な結果を得るのも難しいでしょう。
そこで便利なのが無料の費用シミュレーションツールです。
インターネット上で利用でき、年齢や収入、支出などを入力するだけで簡単にシミュレーションが可能です。
ここでは、そのメリットや注意点、おすすめのツールを紹介します。
4-③-1. 住宅見積もり.com



引用:住宅見積.com (jutaku-mitsumori.com)
住宅見積もり.comは、理想の家を実現するために全国の優良な住宅会社から無料で見積もりを取れるサービスです。
サイトにアクセスし、住宅のタイプや予算などを入力するだけで、最大10社から見積もりが届きます。
比較することで、最適な住宅会社を選べるのがメリットです。
見積もり後は、選んだ会社と詳細な打ち合わせを進めます。時間や労力を節約しながら、コストパフォーマンスの高い家づくりが可能なので、ぜひ活用してみてください。
4-③-2. HOME4U 家づくりのとびら



引用:注文住宅の予算シミュレーション 住宅費用や住宅ローン返済額を簡単算出| HOME4U家づくりのとびら(https://house.home4u.jp/budget/select)
HOME4Uは、家づくりに関する情報やサービスを提供するウェブサイトです。
家づくりの流れや費用、デザインのヒント、施工実例などを掲載し、初めての方でも分かりやすく学べます。
また、厳選された工務店や設計事務所と無料で相談できるため、自分に合った業者を見つけることが可能です。
相談を通じて業者の実力や人柄を確認し、安心して家づくりを進められます。
4-③-3. タウンライフ家づくり



引用:【公式】タウンライフ家づくり|注文住宅の間取りと費用相場の一括比較サイト (town-life.jp)
3分ほどの簡単な入力で自分に合った注文住宅の計画書を作成してくれるのが特徴的です。
また、全国約1030社以上の住宅メーカーがオリジナルプランを届けてくれるので住宅展示場に行く手間や、営業マンとのやり取りが苦手な方にはオススメです。
タウンライフ家づくりは、厳格な国家基準をクリアした信頼のある住宅メーカーのみと提携しているため、安心して利用できます。
ほかにも、以下のことで悩んでいる方にもオススメできます。
- イメージ通りの家を建てるにはいくらかかるんだろう…。
- いろんな住宅展示場を回りたいけど時間がない…。
- そもそも家づくりって何から始めればいいんだろう?
こういった疑問を、タウンライフ家づくりでは家づくりに欠かせない3つのプランで解決してくれます!
- 1. 間取りプラン
- 2. 注文住宅費用
- 3. 土地探し
大手ハウスメーカーから地域密着型工務店まで、さまざまな会社が住みやすい間取りを提案してくれます。
そこから、建物の工事代や土地代や引っ越し代などの総費用を計算して資金計画書を作成してもらえます。
そして、その資金計画書をもとに条件にあった土地探しまでしてくれますよ。
他のカタログ請求サイトとは違い、間取りや資金計画書、土地探しなど、カタログだけでは得られない具体的な情報が手に入ります。
5.ローコスト住宅に関する質問
ローコスト住宅は、一般的な注文住宅に比べて費用を抑えながらも、マイホームを手に入れられる魅力的な選択肢です。
しかし、「なぜ安く建てられるのか?」「品質は問題ないのか?」といった疑問を持つ方も多いでしょう。
ここでは、ローコスト住宅の価格の仕組みや耐久性、設備の自由度について詳しく紹介します。
5-①.ローコスト住宅はなぜ安い?
ローコスト住宅が安い理由は、建材の大量仕入れ、施工の効率化、設備や間取りの規格化にあります。
住宅メーカーはコストを抑えるために、同じ仕様の建材を大量に仕入れたり、標準化された間取りを採用したりしています。
これにより、設計や施工の手間が省かれ、コストダウンが可能になります。
また、オプションを最小限に抑えることで、価格が抑えられている点も特徴です。
例えば、注文住宅では自由に選べるキッチンや浴室のグレードが、ローコスト住宅では標準仕様に限定されていることが多いです。
さらに、人件費削減のために施工を外注せず、自社大工で行うケースもあり、これも価格の低さにつながっています。
ただし、コストを削減する代わりに自由度が低くなる点や、選べる設備に制限がある点には注意が必要です。
5-②.ローコスト住宅の耐久性や断熱性能は大丈夫?
「安い住宅はすぐに劣化するのでは?」と心配する方も多いですが、近年のローコスト住宅は一定の耐久性や断熱性能を確保しています。
ただし、使用する建材や施工方法によって品質に差が出るため、事前にしっかり確認することが重要です。
ローコスト住宅では、コスト削減のために構造材や断熱材のグレードを抑えていることがあるため、標準仕様の耐久性や断熱性能をよく比較しましょう。
例えば、壁の厚さや断熱材の種類が異なると、冬場の寒さや夏場の暑さに影響する可能性があります。
また、耐震性能についても、基本的には建築基準法をクリアしていますが、耐震等級を上げるには追加費用がかかることがあります。
長く安心して住むためには、耐震性の向上やメンテナンスのしやすさも考慮しましょう。
5-③.ローコスト住宅の設備や仕様はどこまで選べる?
ローコスト住宅では、基本的に「標準仕様」が決まっていて、選択肢が限られていることが多いです。
例えば、キッチンやバスルーム、床材などは、あらかじめメーカーが用意したプランの中から選ぶ形になります。
しかし、多くのローコスト住宅メーカーでは、追加費用を払えばグレードアップが可能です。
例えば、標準仕様のキッチンをハイグレードなシステムキッチンに変更したり、外壁の素材を耐久性の高いものに変えたりすることもできます。
ただし、オプションを増やしすぎると、結果的にコストが高くなるため注意が必要です。
6.ハウスメーカー選びに迷っている方へ
家を建てる際に最も重要なのがハウスメーカー選びです。
しかし、多くのメーカーがあり、比較するのも一苦労…
そんな方におすすめなのが、「タウンライフ家づくり」と「LIFULL HOME’S 住まいの窓口」への一括資料請求です。
タウンライフ家づくりでは、希望の間取りプランや見積もりを複数のハウスメーカーから無料で提案してもらえます。
一方、LIFULL HOME’S 住まいの窓口では、専門アドバイザーに相談しながら、条件に合ったメーカーを紹介してもらえるのが魅力です。
この2つを活用すれば、効率よく情報を集め、理想の住宅メーカーを見つけやすくなるでしょう。
まずは気軽に資料請求から始めてみましょう。
\ 間取り、資金計画で悩んでいる方必見!/
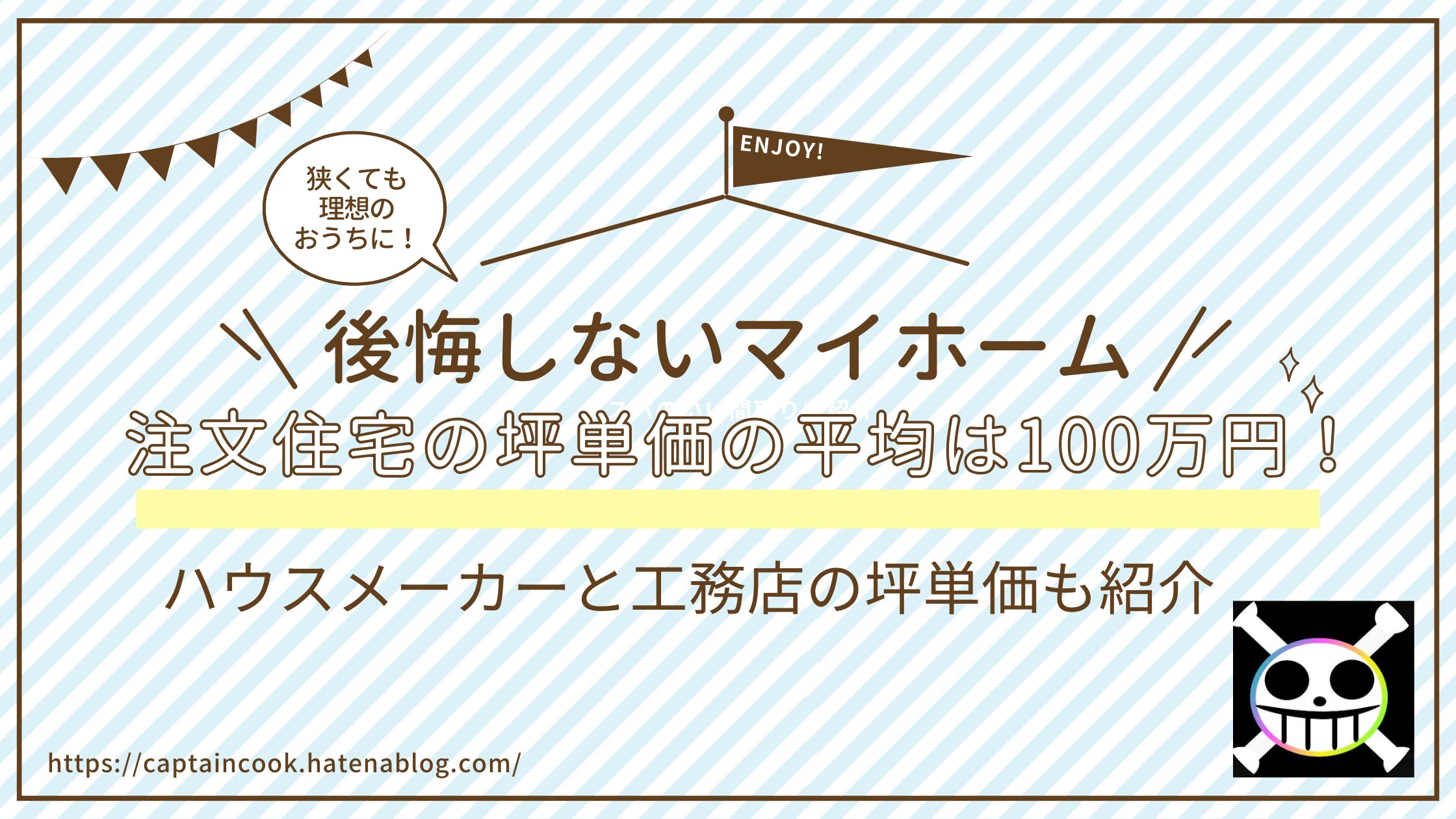
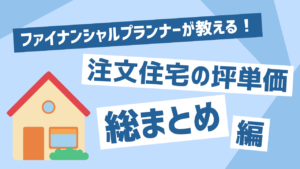
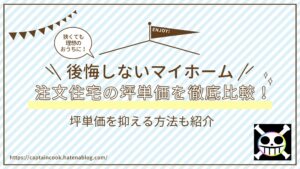
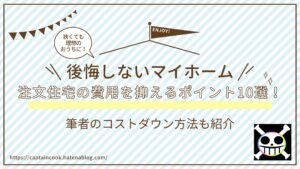
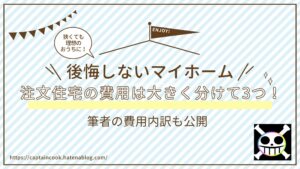
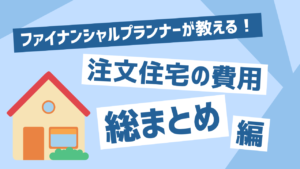



コメント