「費用の内訳を知れば、予算内で理想の家を建てることができる」
まずは、結論としてこの事をお伝えしておきます。
とはいえ、
- 注文住宅の費用ってどれくらいかかる?
- 自分たちの年収で建てることはできるのか?
- みんなはどれくらいお金がかかったのか?
という疑問をお持ちではありませんか?
そこで、この記事ではそんな家を建てるのにどれくらいお金が必要なのかというお悩みを、
実際に注文住宅を建てた筆者の観点から解決します。
具体的には
- 注文住宅の費用が一目でわかる
- 年収別の注文住宅の費用がわかる
- 筆者の費用内訳を公開
の順番にご紹介していきます。
\ 間取り、資金計画で悩んでいる方必見!/
1.注文住宅の費用内訳と割合

家を建てる際に、一番重要になってくるのが予算決めです。
ここで適当に予算を見積もると、実際にハウスメーカーに行ったときに予算オーバーしてしまったということがよくあります。
僕自身も、ネットである程度調べて予算を決めましたが、詳しい費用について知らなかったことで予算オーバーしてしまったんですよね。
ここでは、予算オーバーしないように詳しい費用について解説していきます。
ざっくりと費用の項目を分けると、下記の表になります。
| 地域 | 土地代 | 建築代 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 全国 | 1,819万円 | 3,866万円 | 5,754万円 |
| 三大都市圏 | 2,626万円 | 4,504万円 | 7,130万円 |
土地購入を含む場合は、土地代と建築代の割合は「土地代30%+建築代70%」で予算配分すると良いとされています。



画像引用:お金がかかるのは「建物本体」だけじゃない!建物以外にかかる費用を総チェック|家づくりを知る|My House Palette(マイハウスパレット)|ダイワハウス (daiwahouse.co.jp)
1-①.土地購入費用の内訳(総額の30%)
| 費用内訳 | 内容 | 費用相場 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | 売買契約が成立したときに、その契約を仲介した不動産会社に支払うもの | (物件価格×3%)+6万円×消費税が上限 |
| 売買契約書印紙税 | 土地の売買契約書に貼付する印紙代 | 1,000万円~5,000万円の場合は1万円、5,000万円超1億円以下のときは6万円 |
| 登録免許税(登記費用) | 土地を購入するときは所有権移転登記が必要で、その登記の際にかかる | 土地評価額の1.5% |
| 司法書士報酬 | 登記を司法書士に依頼する場合にかかる | 3万円~5万円程度 |
| 不動産取得税 | 土地や建物を購入したときに一度だけ課せられる税金のこと | 固定資産税評価額×4% |
| 土地購入資金 | |
|---|---|
| 地域 | 平均費用 |
| 全国 | 1,819万円 |
| 三大都市圏 | 2,626万円 |
引用:令和4年度 住宅市場動向調査報告書.pdf (mlit.go.jp)
土地購入資金は、全国平均で1,819万円、三大都市圏平均で2,626万円。このうち自己資金はそれぞれ712万円、1,054万円で、自己資金比率はそれぞれ39.2%、40.1%。
| 費用内訳 | 費用相場 | 全国平均1,819万円の場合 |
|---|---|---|
| 仲介手数料 | (土地価格×3%)+5万円×消費税が上限 | 655,270円※土地価格1819万円 |
| 売買契約書印紙税 | 1,000万円~5,000万円の場合は1万円 5,000万円超1億円以下のときは5万円 | 10,000円 |
| 登録免許税(登記費用) | 土地価格の1.4% | 254,660万円※土地価格1819万円 |
| 司法書士報酬 | 3万円~4万円程度 | 40,000円 |
| 不動産取得税 | 土地価格×3% | 545,700円 |
| 合計 | 1,505,630円 |
注文住宅を建てる場合は、まずは土地が必要になってきます。
土地がない場合は不動産会社やハウスメーカーから購入しますが、その際には表のような諸費用がかかります。
土地購入時の諸費用の詳細を下記にまとめてみたので参考にしてみてくださいね。
1-①-1.仲介手数料
注文住宅の仲介手数料とは、不動産会社が建築会社と顧客をつなぎ、新築の住宅を購入する際に発生する費用のことです。
この手数料は、建築会社から支払われることが一般的で、住宅の価格に一定の割合(通常は売買価格の数パーセント)がかかります。
1-①-2.売買契約書印紙税
土地の売買契約書に貼付する印紙代(印紙税)が必要になります。印紙代(印紙税)は1,000万円超5,000万円以下のときは2万円、5,000万円超1億円以下のときは6万円です。
※2024(令和6)年3月31日までの契約に関しては、それぞれ1~3万円の軽減措置が適用されます。
1-①-3.登録免許税(登記費用)
登録免許税(登記費用)とは、不動産の所有権や担保権の変更を公に登記する際に課される税金や費用のことです。
不動産の売買や贈与、抵当設定などの取引に際して、所有権の移転や権利の設定を法的に確定させるために、不動産登記簿に記載される手続きが行われます。
登記の費用としては、所有権移転登記が5~10万円、家を新築した場合の所有権保存登記は総額で20万円程度、抵当権設定登記なら2~7万円ほどになります。
また、登録免許税の費用相場は「登録免許税=不動産の価格(課税額)×税率0.4%」で不動産の価格(課税価格)に税率0.4%をかけた額が登録免許税となります。
この手続きに伴い、国や地方自治体に登記手続きの料金が支払われることになります。
1-①-4.司法書士報酬
司法書士報酬とは、司法書士が法律的な手続きや文書作成などの専門業務を提供する際に得る対価です。
不動産の登記手続きや遺言書の作成、契約書の調整など、法的な手続きや文書作成に関連する業務を専門的に行う司法書士が受け取る報酬です。
司法書士報酬の費用相場は、5~8万円程度です。
報酬額は、業務の内容や複雑さ、時間、専門知識などに基づいて合意され、業務ごとに異なることがあります。
1-①-5.不動産取得税
不動産取得税は、不動産(土地や建物など)を購入または贈与により取得する際に課される税金です。
取得した不動産の市場価格に一定の税率が適用され、その金額が課税対象となります。
不動産取得税の相場は、2024年(令和6年)3月31日までに取得した建物に対しては、3%(本来は4%)の軽減税率が適用されます。
家屋が居住用でない場合の税率は4%で、計算式は、「固定資産税評価額×税率3%」で計算できますよ。
不動産の売買や贈与などによって所有権が変わる際に、その取引価格や評価額に応じて支払われます。
地方自治体によって税率が異なることがあり、一般的には取引金額が高いほど税額も増加します。
1-②.建物本体工事費用の内訳(総額の75〜80%)
本体工事費用は、注文住宅の本体にかかる費用です。
主な工事の内容は以下の通りになります。
| 本体工事費用の内訳 | 工事の内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 仮設工事費 | 仮設で設置する足場、仮設トイレや安全看板、クレーンなどの揚重設備を設置する費用 | ||||||||
| 基礎工事費 | 建築物の土台である基礎を作る工事で、ベタ基礎・布基礎・独立基礎を行う | ||||||||
| 躯体工事費 | 建物の基礎、柱、梁、床、壁などの骨組みをつくる工事(上棟式) | ||||||||
| 建具工事費 | 窓・引戸・門扉・ドア・ふすまなどの建物の開口部に設けられる開閉ができる仕切り全般のこと | ||||||||
| 内装工事費 | 天井・壁などのクロス張りなど塗装以外の内装工事にかかる費用 | ||||||||
| 外壁工事費 | 外壁の塗装やサイディングなどの作業 | ||||||||
| 空調工事費 | 24時間換気システムや空調ダクトの設置作業 | ||||||||
| 電気工事費 | 電気の配線やコンセントの設置 | ||||||||
| 設備品の設置工事費 | システムキッチン、バス、トイレなどの設置 | ||||||||
| 内装仕上げ工事費 | 壁や天井、床などのクロス貼りする装飾仕上げ工事 | ||||||||
本体工事費用は、総費用の75〜80%程度が相場です。
ハウスメーカーの広告などで記載されている価格は、本体工事費用だけを載せている場合が多いので注意してください。
僕が注文住宅を建てた時は、本体価格からさらに登記や諸費用で+300~500万円は総額でかかりました。
建物本体工事費用の詳細を下記にまとめてみたので参考にしてみてくださいね。
1-②-1.仮設工事費
仮設工事費とは、建築現場や工事現場において、工事の進行や安全確保のために一時的に設置される仮の構造物や施設にかかる費用のことです。
これには仮設の足場、支保工、囲い、作業場所の確保などが含まれます。
新築一軒家の仮設工事費の相場は、50万円前後といわれています。 ただし仮設工事費は、足場の種類によって左右されます。
仮設工事費は、工事全体の進行をスムーズにし、効率的な作業環境を提供するために必要な費用として予算に含まれます。
1-②-2.基礎工事費
基礎工事費とは、建築物や構造物の安定性と耐久性を確保するために行われる、地盤に基礎を築くための工事に関する費用です。
建物の荷重を分散し、地盤の沈下や崩壊を防ぐために、適切な基礎が必要です。
基礎工事にかかる金額は、坪当たりおおよそ40,000~130,000円程度です。
基礎工事費には、地盤調査費、基礎材料(コンクリートや鉄筋)、基礎の形状や深さに応じた掘削・施工費などが含まれます。
建築物や構造物の安全な建設に欠かせない重要な工事です。
1-②-3.躯体工事費
躯体工事費とは、建築物や構造物の骨格部分である躯体(くたい)を構築するための費用です。
躯体は、建物の形状や安定性を支える骨組みであり、主に柱や梁、床、壁などが含まれます。
躯体工事にかかる金額は、木造の場合は坪3~5万円、軽量鉄骨造や鉄骨鉄筋コンクリート造の場合は坪2~8万円と言われています。
躯体工事費には、構造計画に基づいて必要な構造材料(鉄骨、木材、コンクリートなど)の調達費用や加工費、組み立てや施工に関する費用が含まれます。
建物の耐震性や構造の安全性を確保する上で重要な要素であり、建築の中でも大きな費用がかかる部分です。
1-②-4.建具工事費
建具工事費とは、建築物内部のドア、窓、手すり、階段などの設置や仕上げに関する費用です。
建具は建物内の機能やデザインに影響を与える重要な要素であり、建物内部の利便性や美観を向上させる役割を果たします。
建具工事にかかる金額は、取り付ける建具の種類によって異なるので正確な金額を調べることができませんでした。
建具工事費には、建具の種類や材料に応じた調達費用、加工・施工費用、取付け費用などが含まれます。
1-②-5.内装工事費
内装工事費とは、建築物の内部空間を仕上げるために行われる工事に関する費用です。
内装工事は、壁や天井の塗装・クロス貼り、床の張り替え、内部ドアや建具の取り付け、照明や電気配線の設置などを含みます。
内装工事にかかる金額は、坪単価30〜50万円程度といわれています。
建物の使用用途やデザインに応じて内部空間を機能的かつ美しく仕上げるための工程であり、内装工事費には材料の調達費用、施工費用、仕上げの特性に応じた費用が含まれます。
内装工事は、建物の快適性や魅力を向上させるために不可欠な工事です。
1-②-6.外壁工事費
外壁工事費とは、建築物の外部を保護し、美観や耐久性を確保するための費用です。
外壁工事には外壁の塗装、クロス張り替え、サイディングやタイルの取り替え、防水施工などが含まれます。
外壁工事にかかる金額は、屋根+外壁塗装(足場、洗浄、養生、付帯物塗装などをすべて含む)の場合の相場は110~170万円ほどと言われています。
材料費、足場設置費、施工費などが工事費に影響を与えます。
適切な外壁工事により、建物の寿命を延ばし、外観を美しく保つことが可能になります。
1-②-7.空調工事費
空調工事費とは、建築物内の温度や湿度を調整し、快適な環境を提供するために行われる工事にかかる費用です。
空調工事にはエアコンの取り付け、ダクトの設置、暖房や冷房のシステムの組み込み、換気システムの導入などが含まれます。
空調工事にかかる金額は、一般的な空調工事の費用は、10~25万円が相場と言われています。
適切な空調工事により、室内の環境を制御し、快適さや効率性を向上させることができます。
1-②-8.電気工事費
電気工事費は、建築物や施設内で電力供給、照明、通信などのために必要な電気設備を設置するための費用です。
配線の敷設、コンセントやスイッチ、照明器具の取り付け、通信ケーブルの設置などが含まれます。
電気工事にかかる金額は、新築一軒家の場合で50万円程度と言われています。
建物の機能や規模に合わせて電気設備を整備し、安全かつ効率的な利用を実現します。工事費は設備の種類や規模、技術的な要件によって異なります。
1-②-9.設備品の設置工事費
設備品の設置工事費は、建築物や施設内において、設備品(エアコン、排水設備、キッチン機器など)を設置するためにかかる費用です。
これには設備品の取り付け、接続、試運転などが含まれます。
設備品の設置工事にかかる金額は、取り付ける設備の種類などによって異なるので正確な金額を算出することができませんでした。
適切な設備の設置は、機能性や効率性の向上に重要であり、建物の利用価値を高める役割を果たします。
工事費は設備の種類、規模、特定の設置要件によって異なります。
1-②-10.内装仕上げ工事費
内装仕上げ工事費は、建築物の内部空間を美しく整えるための費用です。
壁や天井の加工、床の仕上げ、照明設備の設置などが含まれます。
内装仕上げ工事にかかる金額は、坪単価は30〜50万円程度といわれています。
内装仕上げの費用は、仕上げ材料や作業の難易度、スケールに応じて変動します。
1-③.付帯工事費の内訳(総額の15〜20%)
付帯工事費用は、建物以外にかかる工事費用です。
| 付帯工事費用の内訳 | 工事の内容 |
|---|---|
| 地盤調査・改良工事費 | 地盤を調査して、強度が弱い場合は補強するための工事をする |
| 外構工事 | 門や塀、玄関アプローチ、側溝、駐車場などの工事 |
| 給排水工事 | 給排水、電気、ガス、テレビ、インターネットなど道路から敷地の中まで引き込む工事 |
付帯工事費用は、一般的に総費用の15〜20%が相場です。
カーテン・エアコンや外構工事などは、自分で手配をすれば費用を抑えることもできますよ。
付帯工事費用の詳細を下記にまとめてみたので参考にしてみてくださいね。
1-③-1.地盤調査・改良工事費
地盤調査・改良工事費は、建築物を安定的に支えるための地盤の状態を評価し、必要に応じて改良するためにかかる費用です。
地盤調査によって地下の地質や土壌特性が分析され、建物の荷重に対する安全性が確保されます。
地盤調査・改良工事にかかる金額は、一般的な住宅で5~10万円程度。
地盤改良工事費用は、表層改良で20~40万円程度、柱状改良は40~70万円程度、鋼管杭改良は90~130万円程度です。
地盤改良工事は、地盤の強化や安定化を行うために施工されます。
杭打ち、地下壁の設置、土質改良などが含まれていて、工事費は地盤の状態や改良方法によって異なります。
1-③-2.外構工事
外構工事とは、建物周辺や敷地内の外部空間を整備し、美観や利便性を高めるための工事です。
庭園、駐車場、道路、遊び場などの外部環境をデザインし、舗装や植栽、照明の設置、フェンスの設置などを行います。
外構工事にかかる金額は、100~250万円が目安と言われています。
工事費は設計の複雑さ、使用する材料、敷地の広さなどによって変動します。
1-③-3.給排水工事
給排水工事は、建築物や施設内で水の供給と排水を効率的に行うために行われる工事です。
給水管を通じて水を供給し、排水管を通じて廃水や汚水を排出するシステムを構築します。
給排水工事にかかる金額は、30~50万円程度と言われています。
キッチン、浴室、トイレなどの水利用箇所に給水設備を設置し、使用後の水を安全に排水する仕組みを整えます。
工事には配管の設置、バルブやポンプの取り付け、適切な排水施設の整備が含まれます。
1-④.諸費用(総額の5~7%)
家の建築時には、以下の諸費用がかかります。
| 費用内訳 | 内容 | 費用相場 |
|---|---|---|
| 地盤調査費用 | 工事前に地盤の状態を確認するための費用 | スウェーデン式サウンディング試験は5万円程度 ボーリング調査は25〜30万円程度 |
| 建築確認申請費用 | 設計後、建築基準法に合致しているかどうかを確認するための費用 | 10~20万円程度 |
| 上下水道加入料 | 水道管やガス管などを引き込む際の費用、そのほか自治体に水道加入金等 | 30~50万円程度 |
| 登録免許税(建物表示登記) | 新築住宅を建てた際の建物の登記費用 | 固定資産税評価額×2.0%(0.3%) |
| 登録免許税(所有権保存登記) | 新築建物を取得し、所有権を他の人が主張できないようにするための費用 | 固定資産税評価額×0.4%(0.15%) |
| 司法書士報酬 | 登記手続きを司法書士に依頼する場合の費用 | 3~7万円程度 |
| 設計監理費 | 建物の「設計」と「監理」にかかる費用 | 工事費の10~20% |
| 地鎮祭、上棟式にかかる費用 | 土地に何もない状態で行うのが地鎮祭、基礎工事が完成してから行うのが上棟式 | 10万円前後 |
| 費用内訳 | 費用相場 | 全国平均3,935万円の場合 |
|---|---|---|
| 地盤調査費用 | スウェーデン式サウンディング試験は5万円程度 ボーリング調査は25〜29万円程度 | 50,000円 |
| 建築確認申請費用 | 10~19万円程度 | 190,000円 |
| 上下水道加入料 | 30~49万円程度 | 490,000円 |
| 登録免許税(建物表示登記) | 固定資産税評価額(※本体価格(3,935万円)の70%で計算)×2.0%(0.2%) | 550,900円 |
| 登録免許税(所有権保存登記) | 固定資産税評価額(※本体価格(3,935万円)の70%で計算)×0.4%(0.14%) | 157,400円 |
| 司法書士報酬 | 3~6万円程度 | 60,000円 |
| 設計監理費 | 工事費の10~19% | 7,476,500円 |
| 地鎮祭、上棟式にかかる費用 | 9万円前後 | 90,000円 |
| 合計 | 9,064,800円 |
諸費用は建築工事費用の5~7%程度が目安です。
地盤調査費用は建物を建てる前に、地盤調査を実施して建物を建てても問題ないかを確認するときに掛かる費用です。
地盤に問題がある場合は、約100~120万円ほどの地盤改良費用が掛かってきます。
ライフラインの引き込みは、水道管やガス管などの生活に必要な工事になっています。
また、地鎮祭や上棟式などの費用は数万円程度ですが、積み重ねるとかなりの額になります。
各費用について、さらに詳しく解説していきます。
1-④-1.地盤調査費用
地盤調査費用は建物を建てる前に、地盤調査を実施して建物を建てても問題ないかを確認するときに掛かる費用。
地盤に問題がある場合は、約100~120万円ほどの地盤改良費用が掛かってきます。
ライフラインの引き込みは、水道管やガス管などの生活に必要な工事になっています。
また、地鎮祭や上棟式などの費用は数万円程度ですが、積み重ねるとかなりの額になります。
1-④-2.建築確認申請費用
建築確認申請費用とは、新築や改築などの建築を実行する際に、地方自治体に提出する建築物の設計や計画書類を審査し、法令遵守や安全性確保を確認する手続きにかかる費用です。
建築士に確認申請の書類作成を依頼する場合の費用相場は、15~30万円程度です。
建築の種類や規模、地域によって異なりますが、基本的には建築物の用途や面積に基づいて設定されます。
1-④-3.上下水道加入料
上下水道加入料とは、住宅や建築物に上水道(水道水供給)および下水道(排水処理)への接続を行う際に支払う費用です。
これにより、生活用水の供給と使用後の排水処理が行える環境を整備するための費用です。
上水道加入料の相場は30万~50万円程度です。
上水道加入料は水道供給設備の整備や管路の接続にかかる費用を含み、下水道加入料は排水処理施設の設置や運営に関する費用を含みます。地域や自治体によって料金体系が異なるため、建物の用途や広さ、使用人数などに基づいて加算されることがあります。
1-④-4.登録免許税(建物表示登記)
登録免許税(建物表示登記)は、不動産の所有権移転や抵当権設定などの不動産登記手続きにおいて、新たに建物を登記する場合に課される税金です。
建物の所有者情報や構造などを登記簿に正確に記載し、不動産権利の明確化を図るために支払われます。
登録免許税(建物表示登記)は8~10万円(土地家屋調査士報酬)程度です。
登録免許税額は建物の評価額や所在地、用途などに基づいて計算され、一定の割合が税金として徴収されます。
この税金は不動産の取引や権利設定の際にかかる経費として発生して、地方自治体に収められることで土地の所有権や利用権の確実な履歴を保障し、取引の透明性を確保する役割を果たしています。
1-④-5.登録免許税(所有権保存登記)
登録免許税(所有権保存登記)は、不動産の所有権を確定して、保護するための手続きで発生する税金です。
所有権保存登記では、不動産の所有者が変わらない場合でも、登記簿に正確な情報を記録して、所有権の正当な権利者を明確に示すことが重要です。
所有権保存登記の費用相場は、3万円(司法書士報酬)程度です。
この手続きによって、不動産に関する権利関係が法的に確認され、不正な権利の主張や紛争を未然に防ぐ役割を果たします。
所有権保存登記に伴う免許税は、登記の際に発生し、土地の評価額や地域によって異なる割合で課税されます。
これにより、不動産権利の透明性と安定性を維持し、不動産取引の信頼性を確保することができます。
1-④-6.司法書士報酬
司法書士報酬とは、司法書士が法律的な手続きや文書作成などの専門業務を提供する際に得る対価です。
不動産の登記手続きや遺言書の作成、契約書の調整など、法的な手続きや文書作成に関連する業務を専門的に行う司法書士が受け取る報酬です。
司法書士報酬の費用相場は、5~8万円程度です。
報酬額は、業務の内容や複雑さ、時間、専門知識などに基づいて合意され、業務ごとに異なることがあります。
1-④-7.設計監理料
設計監理料は、建築プロジェクトにおいて建築設計や施工工事の過程で、設計者や監理者が行う業務に対する報酬です。
建築の設計段階から施工・完成までの間、建築物の計画や仕様に従って進行を監視し、品質やスケジュールの遵守を確保する役割を果たします。
設計監理料の費用相場は、建築工事費の10%程度になります。
設計監理料は、建築計画や施工の複雑さ、規模、工程などに基づいて合意され、一定の割合で報酬が支払われます。
1-④-8.地鎮祭、上棟式にかかる費用
建築を始める前に地鎮祭を行う場合には、3~4万円ほどの費用がかかります。ま
た、建物の骨組みが出来上がったときに上棟式を行う場合には、ご祝儀や昼食代などが必要です。
費用は地域にもよるので、ハウスメーカーなどの担当者に尋ねてみましょう。
2.【年収別】注文住宅の費用内訳
![[By annual income] Image of cost breakdown of custom-built housing](https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/u/uzumaki1121/20230818/20230818080605.jpg)
![[By annual income] Image of cost breakdown of custom-built housing](https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/u/uzumaki1121/20230818/20230818080605.jpg)
![[By annual income] Image of cost breakdown of custom-built housing](https://cdn-ak.f.st-hatena.com/images/fotolife/u/uzumaki1121/20230818/20230818080605.jpg)
住宅購入を検討し始めた方の中には、「家を建てるにはいくらくらいの年収が必要なの?」「みんなはどの程度の年収で家を購入しているの?」と疑問に感じている方も多いのではないでしょうか。
国土交通省の「令和4年度 住宅市場動向調査報告書」によれば、注文住宅の一次取得者(初めて注文住宅を購入する人)で最も割合の多い世帯年収(税込)は600万円~800万円。
世帯年収は全国平均で801万円、三大都市圏の平均で896万円です。
それでは、年収別に費用の相場を紹介していきます。
| 年収 | 借入額の目安 | 月々の返済 |
|---|---|---|
| 300万円 | 2,361万円 | 7.5万円 |
| 500万円 | 4,592万円 | 14.6万円 |
| 700万円 | 6,428万円 | 20.5万円 |
【算出条件】
・シュミレーションツール:新規借入れを検討の方:長期固定金利住宅ローン 【フラット35】 (flat35.com)
・金利は1.73%で計算
・返済負担率25%
・返済期間35年
・元利均等返済(毎月定額を返済する方法)
・頭金なし、ボーナス時加算額なし
年収別の費用相場を3パターンの年収に分けて紹介していきます。
自分の年収に近い費用相場を知っておくことで、理想と現実のギャップが少なくなるのでオススメです。
2-①.【年収300万円】の費用相場と無理のない予算額
【年収300万円の費用相場】
| 年収 | 借入額の目安 | 月々の返済 |
|---|---|---|
| 300万円 | 2,361万円 | 7.5万円 |
【年収300万円の無理のない予算額】
| 年収 | 年収×年収倍率(5倍) | 年収×年収負担率(25%) |
|---|---|---|
| 300万円 | 1,500万円 | 年間75万円 |
十分な貯蓄がある人以外は、年収300万円で注文住宅を建てるためには資金の借り入れが必要になります。
借り入れして住宅ローンを組む際に、購入予算(=借り入れ金)を決めるための指標となるのが「年収倍率」と「返済負担率」です。
年収倍率とは、世帯年収に対する物件購入価格の比率のことです。
一般的には、年収倍率は約5倍までが健全に返済できる金額とされています。
返済負担率とは、年収に対する年間返済額の割合のことで、一般的に無理のない返済負担率は25%以内とされています。
手取り額の目安は、一般的に額面収入の75%~85%といわれており、年収300万円の場合の手取り年収は、216万~255万円程度となります。
一般的に住宅ローンは年収の5~6倍が適正とされています。
そのため、年収300万円なのであれば1,500~1,800万円までがおおよその住宅ローンの目安となるでしょう。
そこから計算すると年収300万円の方の返済可能額は、返済負担率25%の年間返済額75万円となります。
しかし、これはあくまでも目安であって、理想の数字とはいえません。
返済可能額は極力無理なく返済できる範囲にして、実際にはより少なくなくするのが大切です。
土地付注文住宅であれば建物の建築費用に加え、土地の購入費用がかかるため、できるだけ建物にこだわりたいのであれば、土地購入のコストを抑える必要があります。
「最寄駅からやや離れている」「坪数の少ない土地」など、同じエリアで同じぐらいの広さであっても土地の立地条件次第では、建築制限などの規制がある分、比較的安くなっている場合もあります。
また「実家が敷地の広い」のであれば、敷地の一角を譲り受けて建てることで土地購入の費用を抑えられ、その分を建築費用に回すことができます。
2-②.【年収500万円】の費用相場と無理のない予算額
【年収500万円の費用相場】
| 年収 | 借入額の目安 | 月々の返済 |
|---|---|---|
| 500万円 | 4,592万円 | 14.6万円 |
【年収500万円の費用相場】
| 年収 | 年収×年収倍率(5倍) | 年収×年収負担率(25%) |
|---|---|---|
| 500万円 | 2,500万円 | 年間125万円 |
年収500万円というと、平均給与よりも高い金額です。
しかし、実際の手取り額から試算すると建てられる家の規模は限られてきます。
手取り額の目安は、一般的に額面収入の75%~85%といわれており、年収500万円の場合の手取り年収は、375万~425万円程度になります。
借り入れして住宅ローンを組む際に、購入予算(=借り入れ金)を決めるための指標となるのが「年収倍率」と「返済負担率」です。
年収倍率とは、世帯年収に対する物件購入価格の比率のことで、一般的には年収倍率は約5倍までが健全に返済できる金額とされています。
返済負担率とは、年収に対する年間返済額の割合のことで、一般的に無理のない返済負担率は25%以内とされています。
年収500万円で年収倍率は約5倍とした場合は、2,500万円。
返済負担率を20~25%と設定した場合、ローンの返済期間にもよりますが、借入限度額の目安は2,400万~3,400万円前後になります。
頭金をある程度用意できれば、購入可能額はさらに増やすことが可能な世帯年収です。
2-③.【年収700万円】の費用相場と無理のない予算額
【年収700万円の費用相場】
| 年収 | 借入額の目安 | 月々の返済 |
|---|---|---|
| 700万円 | 6,428万円 | 20.5万円 |
【年収700万円の費用相場】
| 年収 | 年収×年収倍率(5倍) | 年収×年収負担率(25%) |
|---|---|---|
| 700万円 | 3,500万円 | 年間175万円 |
年収700万円の借入可能額は3500万万円が一つの目安になってきます。
この目安は、「年収倍率」と「返済負担率」から計算しています。
年収倍率とは、購入する住宅価格が年収の何倍になるか表した数値のことで、金融機関が融資額を決める際の判断材料にも使われています。
一般的に適正な年収倍率は5~6倍と言われていて、年収700万円だと3500~4200万円が借入可能額の目安となります。
返済負担率とは、年収に対する年間返済額の割合のことで、一般的に無理のない返済負担率は25%以内とされています。
年収700万円の毎月返済額の目安は14万6,000円。
返済負担率を25%と想定すると、年収700万円の世帯における毎月返済額の目安は「700万円÷12ヶ月×25%=約14万6,000円」となります。
そのため、14万6,000円以内であれば、基本的には無理なく返済していけると考えられます。
>>注文住宅の費用を抑えるポイント10選!注意する点と筆者のコストダウン方法も紹介
3.筆者の注文住宅の費用内訳を公開



ここまで紹介してきた費用の内訳は、一般的なものをまとめたものになります。
ここからは、実際に筆者の私がタマホームで建てた際に掛かった費用の内訳を紹介していこうと思います。
土地購入費用ですが、私の実家の土地が空いていたのでそこを分筆したため土地代はかかっていません。
しかし、分筆の際に登記や分筆費用など様々な費用がかかりました。
平均的な費用の内訳とは違う部分も多いので、これから紹介する費用の内訳の方がより現実に近いですよ。
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 総工事費合計 | 19,353,294円 |
| 土地購入費 | 0円 |
| ご紹介工事 | 0円 |
| その他費用・諸費用 | 4,103,944円 |
| 合計 | 23,457,238円 |
| 項目 | 金額(税込) |
|---|---|
| 自己資金 | 4,457,238円 |
| 借入金額 | 19,000,000円 |
| 合計 | 23,457,238円 |
注文住宅の総額はすべて含めると、23,457,238円になりました。
初めに予算を立てたときからかなり値段がかかりました。
実家の土地を活用できたのでよかったですが、土地がなければさらに金額は上がっていました。
月々の返済を6万円台にしたかったので、オプションは最低限のものとエアコン、照明、カーテン工事や引っ越し業者の手配は自分で行い約50万円ほどになりました。
これらをタマホームでやると、倍の100万円以上になっていたのでコストを削減できてよかったです。
3-①. 建物本体工事費用の内訳(総額の63.6%)
| 項目 | 延床面積(㎡) | 延床面積(坪) | 金額(税込) |
|---|---|---|---|
| 本体工事 | 108.49 | 34.56 | 14,928,304円 |
| 施行面積 | 114.28 |
建物の本体価格は約35坪で14,928,304円。
最初は21坪の3LDKにしようとしていましたが、老後に1階にも1部屋あった方がいいんじゃないかと親から言われたのがきっかけで4LDKにしたため約1500万円ほどになりました。
価格を抑えるために間取りを少なくするのは必要なことですが、後々のことを考えて増築するより値段を抑えることができるのでいい選択だったかなと感じています。
3-②.オプション工事費用の内訳(総額の0.3%)
| オプション工事 | 金額(税込) |
|---|---|
| 増設 2枚引違26511シャッター | 67,590円 |
| 天井点検口増設(240×240) | 7,710円 |
| 合計 | 75,300円 |
オプションでかかった合計は75,300円になりました。
オプションをつけると値段が跳ね上がるのはわかっていたので、なるべくオプションをつけないように意識していました。
ですが、標準仕様だと雨戸のシャッターがついてない窓もあり危険だと思ったので追加で付けることにしました。
ほかにも、その他費用のほうで計上していますがコンセントも追加しています。
コンセントをオプションで追懐した理由は、後付けの方が値段が高いからなんです。
実際に住んでいない状況でコンセントの数を考えるのは大変でしたが、なるべく部屋に均等にコンセントがあるようにすることで、実際に住んでいる今はコンセントが少なかったという不満はありません。
3-③.付帯工事費の内訳(総額の約7.1%)
| 付帯工事 | 金額(税込) |
|---|---|
| 屋外電気配線工事 | 1式 |
| 屋外給排水工事 | 1式 |
| 屋外立水栓工事 | 1カ所 |
| 雨水排水工事 | 1式 |
| 仮設費用 | 1式 |
| 下水道接続工事 宅内接続 | 1式 |
| 合併浄化槽工事 耐圧有 5人槽 | 1式 |
| 簡易水洗便槽工事 | 1式 |
| 合計 | 1,664,000円 |
付帯工事でかかった金額は1,664,000円になりました。
付帯工事の費用の詳細な内訳はわからないのですが、コストを下げるのは難しいところだと思います。
工事の内容も専門的な言葉が多くて、事前に注文住宅の本を読んでいた僕でも全く費用相場がわからなくて勉強不足でした。
事前にもっと勉強していれば、この部分もコストを抑えられたかもしれないという思いがあるので、皆さんには事前に注文住宅の基礎知識は身に着けておくのをオススメしたいです。
3-④.必要費用(総額の約3.9%)
| 必要費用 | 金額(税込) |
|---|---|
| 基本図面作成料 | 1式 |
| 設計料 | 1式 |
| 地盤調査 | 1式 |
| 工事管理費 | 1式 |
| 諸検査費用 | 1式 |
| 住宅瑕疵保険料 | 1式 |
| 長期優良住宅認定費用 | 1式 |
| 合計 | 926,300円 |
必要費用で掛かった費用は926,300円になりました。
この費用も付帯工事と同じで、コストダウンが難しい項目です。
内訳も専門的な内容が多くて、詳細な金額は把握できませんでした。
コストを削減するには、オプションや外構工事などを削るのが一番いいですよ。
3-⑤.諸費用(総額の約7.1%)
| 諸費用 | 金額(税込) |
|---|---|
| 建物登記費用(表示・保存・設定) | 235,550円 |
| 分筆および農地転用・地目変更費用 | 689,300円 |
| 火災保険料 | 130,440円 |
| 印紙税(住宅ローン契約書用) | 20,000円 |
| 融資手数料 | 33,000円 |
| ローン保証料(現金一括払い) | 356,537円 |
| つなぎ融資利息・手数料 | 183,000円 |
| 農協出資金 | 10,000円 |
| 合計 | 1,657,827円 |
諸費用で掛かった費用は1,657,827円になりました。
この諸費用の部分では、コストを下げられる部分がいくつかあります。
まずは火災保険料で、タマホームでは3パターンぐらいの保険がありましたがその中でも一番安い保険料にしました。
僕はタマホームからの紹介で火災保険の会社を決めましたが、自分で火災保険を見つけることでさらにコストを抑えることもできますよ。
他にも、融資手数料とローン保証料は各銀行によって違うのでどこの銀行からお金を借入するかがコストを下げるポイントになります。
僕の場合はタマホームからの提案もありましたが、自分で3つの銀行を実際に回って最終的にJAバンクで借入をしました。
自分で借入先を決めるのは大変でしたが、これから35年払い続けていくのでなるべく好条件の銀行を探すことができてよかったです。
3-⑥.その他費用(総額の約8.7%)
| その他費用 | 金額(税込) |
|---|---|
| 水道加入金および接続工事費等 | 91,300円 |
| 地鎮祭費用 | 30,000円 |
| 上水道引き込み工事 | 512,205円 |
| 電気配線工事 | 165,000円 |
| 排水管変更工事 | 309,100円 |
| 追加工事費用 | 806,179円 |
| アンテナ工事費用 | 126,700円 |
| 合計 | 2,040,484円 |
その他費用に掛かった金額は2,040,484円になりました。
項目には書いていないですが、地盤改良費用がかかっていないのが大きなコストダウンにつながりました。
地盤改良費用とは、地盤調査をして地盤に問題があれば補強する工事なのですが実家の土地の地盤が強かったため必要ありませんでした。
地盤改良費用を行うと約100万円はしたので、助かりました。
他にもアンテナ工事ですが、僕はタマホームでお願いしましたが家電量販店だと半額くらいでできることもあるのでコストをもっと抑えたい方は自分で手配するのもオススメです。
3-⑦.エアコン、照明、カーテン工事+引っ越し費用(総額の約2.1%)
| 工事・費用 | 金額(税込) |
|---|---|
| エアコン工事 | 222,200円 |
| 照明工事 | 25,800円 |
| カーテン工事 | 157,633円 |
| 引っ越し費用 | 87,000円 |
| 合計 | 492,633円 |
こちらの掛かった金額は492,633円になりました。
タマホームで行うと、倍以上の金額になるので自分で手配してよかったなと思いました。
正直自分で家電量販店やカーテン屋さんに行って決めるのは大変でしたが、なるべく費用を抑えるならできるところは自分で行うのが良いですよ。
手間と時間はかかりますが、注文住宅以外にも将来必要なお金はたくさんあるので少しでも削っていきましょう。
>>注文住宅の費用を抑えるポイント10選!注意する点と筆者のコストダウン方法も紹介
4.ハウスメーカー選びに迷っている方へ
家を建てる際に最も重要なのがハウスメーカー選びです。
しかし、多くのメーカーがあり、比較するのも一苦労…
そんな方におすすめなのが、「タウンライフ家づくり」と「LIFULL HOME’S 住まいの窓口」への一括資料請求です。
タウンライフ家づくりでは、希望の間取りプランや見積もりを複数のハウスメーカーから無料で提案してもらえます。
一方、LIFULL HOME’S 住まいの窓口では、専門アドバイザーに相談しながら、条件に合ったメーカーを紹介してもらえるのが魅力です。
この2つを活用すれば、効率よく情報を集め、理想の住宅メーカーを見つけやすくなるでしょう。
まずは気軽に資料請求から始めてみましょう。
\ 間取り、資金計画で悩んでいる方必見!/
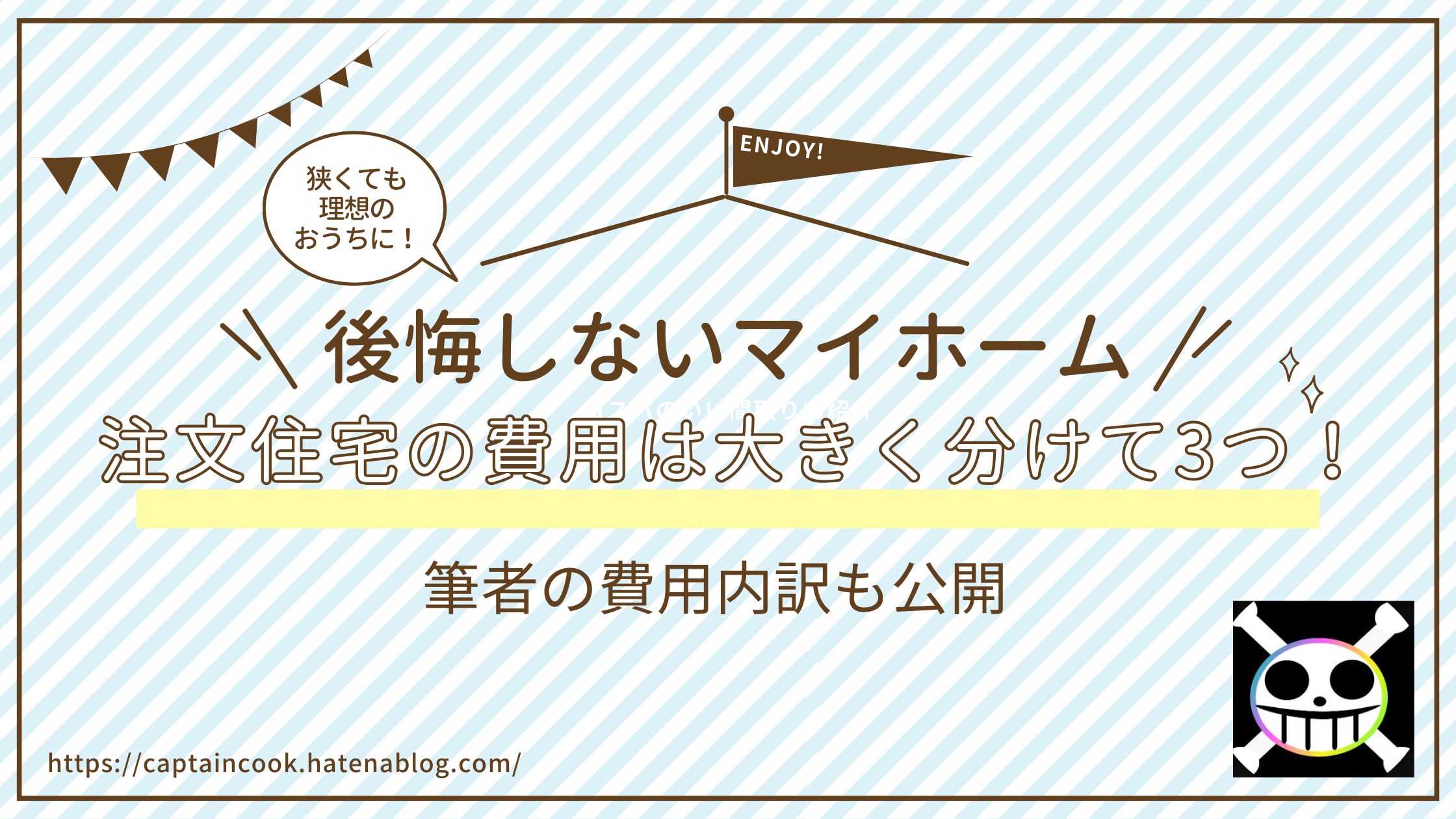
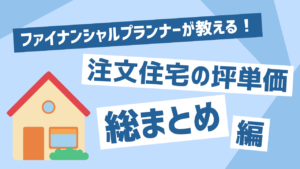
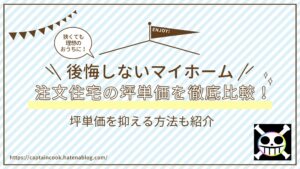
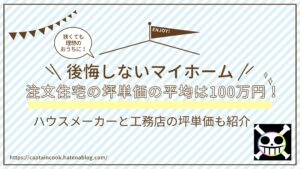
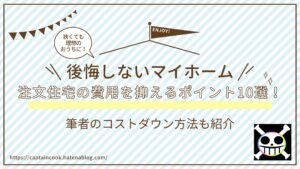
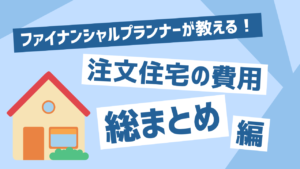



コメント