「注文住宅の間取りを理解すれば、予算内で理想の家を建てることができる」
まずは、結論してこの事をお伝えしておきます。
とはいえ、
- 自分たちの予算だと、どのくらいの家が建てられる?
- オススメの間取りは?
- 間取りの決め方がわからない
- 予算別の間取りが知りたい
という疑問をお持ちではありませんか?
そこでこの記事ではそんな間取りの決め方が分からないというお悩みを、
タマホームで実際に注文住宅を建てた筆者の観点から解決します。
具体的には
- 注文住宅の間取りの決め方
- 間取りの後悔した点と後悔しないポイント
- 注文住宅の間取り別の価格
- 2000万円台に抑えるための間取りの決め方
- おすすめの間取り9選!
- 筆者の間取りを公開
の順番にご紹介していきます。
\ 間取り、資金計画で悩んでいる方必見!/
1.注文住宅の間取りの決め方

注文住宅の間取りを決める際には、家族全員が快適に暮らせる工夫が欠かせません。
間取りを考える際には、以下のポイントを押さえておきましょう。
・家族構成に合った部屋の数にする
・普段の生活動線・家事動線を意識する
・ライフステージの変化に対応できる間取りにする
これらのポイントについて、下記で詳しく紹介していきます。
1-①.家族構成に合った部屋の数にする



下の表に、家族構成別に必要な間取りの目安を一覧にしてみました。
一般的な家族構成をもとに紹介しましたが、より自分たちの生活の状況をしっかりと把握するのが大事です。
例えば、夜勤や早朝出勤がある方がいる家庭は、各自が個室を持った方がお互いにストレスなく過ごせるかもしれません。
一般的な間取りにとらわれず、今の自分たちの生活と今後の生活の変化を予測して決めていくと後悔がなくなりますよ。
1-②.普段の生活動線・家事動線を意識する



1-③.ライフステージの変化に対応できる間取りにする



ライフステージの変化に対応できる間取りであれば、暮らしやすさを長期にわたって維持できます。
変化があった場合も長く暮らせる家の特徴には、『バリアフリーな間取り』『可変性のある間取り』の2つが取り入れられています。
バリアフリーな間取りは、個室のいくつかを1階にすることで、老後の足腰にトラブルを抱えても生活しやすさを維持しやすくなります。
可変性のある間取りでは、しまえる引き戸などを使って間仕切りができるようにすれば、子供部屋が将来必要ない時に間仕切りで両親の趣味の部屋として使うことも可能です。
2.間取りの後悔した点と後悔しないためのポイント



注文住宅は自由に間取りを決められる魅力がありますが、実際に住んでみると「もっとこうすればよかった」と後悔することも少なくありません。
・注文住宅の間取りで後悔したこと11選!
・後悔しないためのポイント
ここでは、注文住宅の間取りでよくある後悔ポイント11選と、後悔しないための具体的なポイントを詳しく紹介していきます。
2-①.注文住宅の間取りで後悔したこと11選!



ここを適当に決めてしまうと、後々後悔することになります。
でも、僕自身もかなり考えたつもりで間取りを決めましたが、今になってこうしておけばよかったということが出てくるんですよね。
ここでは、なるべく皆さんの間取りの後悔をなくせるように自分自身の体験と一般的な間取りの後悔ポイントを合わせて紹介していきます。
次の章では、項目別に詳しく解説していきますね。
| 注文住宅の後悔ポイント | 項目 | |
|---|---|---|
| ・玄関が狭い | 間取り | |
| ・子供部屋が足りない | 間取り | |
| ・ベランダがいらなかった | 間取り | |
| ・キッチンの高さが合っていない | 設備 | |
| ・床暖房の電気代が高い | 設備 | |
| ・コンセントの数と位置が悪い | 設備 | |
| ・壁紙の色と柄がイメージと違う | デザイン | |
| ・家具や家電を壁付けにしたが模様替えできない | デザイン | |
| ・予算オーバーした | 費用 | |
| ・追加オプションが高い | 費用 | |
| ・メンテナンス費用が高い | 費用 | |
2-①-1.玄関が狭い



玄関が狭いと、靴をしまうスペースが少なかったり、家族で出掛けるときに窮屈に感じたりとけっこう不便です。
僕も玄関の狭さには後悔していて、図面だと広く感じたけど実際は下駄箱などがあって狭く感じてしまいます。
玄関は、家族が増えることや老後のことを考えて、広めにつくっておくといいですよ。
2-①-2.子供部屋が足りない



子供部屋が足りないのは、未然に防ぐことができます。
それは、子供の人数をあらかじめ予想して間取りを決めること。
部家が余ってしまったり、予算オーバーになると思った方はいませんか?
確かに、僕も部家が余ってしまったりしたらもったいないと思いましたが、子供部屋は2部屋作っています。
なぜかというと、増築にはお金がかかるし、もし部家が余っても老後の部屋や物置部屋としての機能も果たせるので作りました。
予算の兼ね合いもありますが、余裕のある間取りにしておくといいですよ。
2-①-3.ベランダがいらなかった



ベランダを使うか使わないかでかなり意見が分かれると思います。
僕の場合は、部屋干し派でベランダは要りませんでしたが、間取りと予算の都合で付けることになりました。
理由は、ベランダのところを部屋にすると、コストが余分に掛かってしまうんですよね。
なので、ベランダにしてコストを抑えることにしました。
ベランダを付けることで、子供がベランダに出て落ちてしまう危険もありますし、今の時代は部屋干しように天井から物干し竿を垂らすこともできます。
2-①-4.キッチンの高さが合っていない



ご自宅のキッチンの高さは適切でしょうか?
あまり考えたことはなかったかもしれませんが、キッチンには使う人にとってはかなり重要になってきます。
キッチンの高さが合わないことで腰痛、首痛、肩こりなど身体の様々な場所でトラブルが発生します。
住宅展示場や打ち合わせの時に事前にキッチンの高さについては相談しますが、実際に使っていくうちに細かい作業の時に高さが合わないという思いが出てきてしまうんですよね。
キッチンの標準的な高さは85cmですが、自分の家族構成やライフスタイルに合わせて高さを決めてみてください。
2-①-5.床暖房の電気代が高い



足元からじんわりと部屋全体を暖めてくれる床暖房はかなり便利です。
そのため、マイホームにつけたいと考えている人も多いのではないでしょうか。
魅力的な床暖房ですが、実は知らないと後悔するポイントが出てきてしまいます。
・電気代が高くついた
・メンテナンス費用がかかる
床暖房をつけた方は、上記のことで悩んでいませんか?
床暖房は10帖のリビングに設置する場合「50~100万円」かかります。
床暖房を導入するときは、デメリットも把握したうえで床暖房の導入を検討してみてください。
2-①-6.コンセントの数と位置が悪い



住まいの中でも多くの家電が集まるキッチンでは、コンセントの数が足りなかったり・位置が悪かったりすると、料理がしにくく後悔ばかりのキッチンになってしまいます。
設計士から提案されたプランの通りにコンセントの配線計画をしても、実際に生活してみると「コンセントの数が全然足りなかった・・・」という話は良くあることです。
後からコンセントを増設することもできますが、設置場所によっては増設が難しく、費用が数万円以上かかることもあります。
コンセントの失敗や後悔を防ぐために、マイホームでの暮らし・家族それぞれの部屋での過ごし方を、上手にイメージしてみてください。
2-①-7.壁紙の色と柄がイメージと違う



部屋の壁紙を好きな色・柄で選んだはずなのに、いざ部屋に入ったとき「あれ?なんかイメージと違う!」と感じたことはありませんか?
これは、サンプルの色を見ている時、意識せずにサンプルの台紙も見てしまっているのが原因なんです。
台紙の色によって、サンプルの色が違って見えますし、面積の小さいサンプルの色は台紙の影響を受けやすくなっています。
このイメージの違いをなくすためには、なるべく大きな見本サイズで確認するのが大事です。
依頼する住宅会社で過去に採用実績のあるものや、仕上がりのイメージを共有できるモノを選ぶようにしましょう。
2-①-8.家具や家電を壁付けにしたが模様替えできない



家具や家電を壁掛けにすると、壁紙をすぐには変更できないんですよね。
壁掛けテレビは壁に穴を開けて、専用の金具を取り付けて壁に固定しています。
テレビの位置を変えるときは、また壁に穴を開けて金具を取り付ける必要があります。
ほかにも、空いた穴を塞いだり壁の強度によっては壁掛けを移動できないこともデメリットです。
2-①-9.予算オーバーした



注文住宅は予算を組んでいても、オーバーしてしまうことが多いです。
主な原因として、「予算の見積もりミス」「地盤改良」「外構」の3つに分かれます。
予算の見積りミスは、家の本体価格だけを見ていることで起きます。
付帯工事や諸費用の分を入れるとかなりの金額になるので、事前にすべての金額を把握しておくのが大事です。
地盤改良については、する場合としない場合があります。
これは、その土地の強度によって地盤改良工事が必要になってくるからなんです。
最後の外構に関しては、自分が外構工事をしたいかで値段が変わってきます。
僕自身は、外構工事にお金をかけることができなかったので、外構工事はしませんでした。
2-①-10.追加オプションが高い



オプションの中には、数千円のオプション品から百万円を超えるほどのオプション品があります。
家の購入金額自体が高額のため、数千円のオプションを躊躇なく付けてしまった方も多いんじゃないでしょうか?
この積み重ねでオプション料金が上がってしまったり、標準仕様に満足できないとかなりのオプションを付けてしまって高くついてしまうことがあります。
後々後悔しないためにも、標準仕様以外に自分たちにとって本当に必要なものは何か?をしっかりと考えてみるのが大事です。
僕の場合は、コンセントが標準仕様でついている数が少なかったので、後々増設するよりオプションの方が安かったのでオプションでコンセントの数を追加しました。
2-①-11.メンテナンス費用が高い



注文住宅を建てる際には、土地の購入費や建物の建築費を気にしますが、家を建てた後にも様々な費用がかかります。
10年、20年先のことなので今すぐに必要なわけではありませんが、事前に準備をしておかないと将来困ってしまうことにもなりかねません。
主なメンテナンス場所は、火災保険の更新、ガス給湯器の故障と買い換え、エアコンの故障と修理、洗濯機の買い換えなどがあります。
一般的な住宅では約30年のメンテナンス費用として、「400万円〜500万円」くらいのメンテナンス費用が必要になります。
2-②.後悔しないためのポイント



では、どうすれば間取りの失敗を避けることができるのでしょうか?
この章では、注文住宅の間取りを決めるときに注意すべきポイントをご紹介します。
2-②-1.将来まで考えた間取りにする



例えば、子どもが増えれば、その分部屋も必要になりますし、勉強机なども置くのである程度の部屋の広さも考慮しないといけません。
子供が独立して、夫婦が年を重ねれば、バリアフリーへの対応も必要になってきます。
途中でリフォームする方法もありますが、余計な出費が必要になったり、リフォームできないところも出てくる可能性があります。
今の段階ですべてを見通すことは難しいかもしれませんが、自分たちの将来設計をなるべく細かく間取りに反映させていくのが大事です。
2-②-2.資金計画は余裕を持たせる



年収の30%以内に収めることで、住宅ローンの返済が生活費を圧迫することがありません。
資金計画を立てる際には、ネット上で使える無料の予算シミュレーションツールを使って自分がいくらぐらい払えるのかを事前にチェックしておきましょう。
また、ハウスメーカーから見積書をもらったら、見積書に含まれていない追加費用はいくらぐらいになるのかも担当者に聞いておくのがいいですよ。
2-②-3.コンセントの位置と数は具体的に



自分たちの今までの生活を考えて、事前にイメージして書き出しておくと必要なコンセントの数も見えてきますよ。
例えばキッチンの場合、どんな家電を置くのかなど書き出してみましょう。
炊飯器、電子レンジ、オーブンを置きたいなら、最低3口はコンセントが必要になります。
他にも、ルンバを使うのであればクローゼットや収納内に充電用のコンセントがあると便利です。
後で改修工事を行うこともできますが、増設にはかなりの費用が発生するので事前に確認しておきましょう。
2-②-4.オプション追加は優先順位をつける



予算の問題もあるので、自分たちの暮らしに本当に必要な設備なのか、どのくらいの頻度で使うのかなどをしっかりと家族で話し合いましょう。
浴室暖房乾燥機、食器洗浄機、ウッドデッキなどは、最初のうちは使うことも多いですが時間とともに使わなくなる方も出てきます。
家の購入となると何千万ものお金が動くので、オプションの数万円が安く感じてしまいますが、自分にとっての優先順位をしっかり考えてみてください。
3. 注文住宅の間取り別の価格



ここで、自分の予算と間取りがマッチするかを見ていきましょう。
予算次第では、間取りの調整をしないといけなかったり部屋数などを変更しないといけなくなります。
間取り別の価格をある程度知っておくことで、自分の予算との開きを確認できますし、間取りづくりの一定の基準が出来上がります。
3-①.1LDK~2LDKは『1000万円以内の家』
一番安いローコストな家を建てたいと考える方にオススメなのは「1,000万円以下」のローコスト住宅です。
しかし、1000万円以下のローコスト住宅の商品数が少なくて、多くは平屋のローコスト住宅になります。






引用:19坪平屋プラン|1000万円以下の平屋 | はなまるハウス (870house.jp)
1,000万以内に予算をおさめるためには、家のグレードや材料や設備オプションをかなり削らないといけません。
一般的な家と比べると狭いので、家族の人数が少ない方にはオススメです。
3-②.2LDK~4LDKは『1000万円台の家』
1000万円台の家はローコストハウスメーカー・中堅ハウスメーカーが主力商品として販売しています。
比較的に広い平屋から2階建ての住宅まで建てることができます。






ただし、外観やデザイン、間取りはシンプルになる可能性が高いです。
間取りやデザインはシンプルですが、耐震性や断熱などは申し分ないので、こだわりがない方にはオススメです。
>>ローコストのおすすめ注文住宅ランキング!メリット・デメリットや選び方を解説
3-③.2LDK~5LDKは『2000万円台の家』
4人家族以上の住宅を建てる際に、中堅ハウスメーカーだと、こだわりたい部分をグレードやオプション追加することができます。
この価格帯なら、大手のハウスメーカーの標準仕様の住宅も建てることが可能になります。






引用:家づくりをインターネットで楽しむ|住宅ネット|タマホーム株式会社 (jutakunet.com)
高いデザイン性や材木の素材などは妥協しないといけませんが、それ以外のオプションを追加したい方にはオススメです。
3-④.3LDK~6LDKは『3000万円台の家』
3,000万円台の家は、大手ハウスメーカーの標準仕様だけでなく、仕様変更できたり、設備のオプションを加えたりすることが可能な価格帯です。






引用:家づくりをインターネットで楽しむ|住宅ネット|タマホーム株式会社 (jutakunet.com)
こだわりたい部分を比較的に実現しやすいですし、間取りやデザイン性も理想の家に近づけることができます。
ほかにも、大手ハウスメーカーはアフターサービスの条件もいいので、将来的なメンテナンス費用が節約できるというメリットもあります。
>>【徹底解説】おすすめローコスト住宅ランキング10選!費用を抑えるポイントも紹介 – クック船長のローコスト住宅ブログ
4.2000万円台に抑えるための間取りの決め方



そのためには、以下のようなポイントを考慮することが重要です。
ただし、建築費用を削減するために犠牲にすることで、使用者のニーズや使用目的に合った設計ができないこともあるため、それらをバランスよく考慮しながら、設計を進めることが重要です。
下記に2000万円台以内に収めるポイントをまとめてみました。
4-①.広さや設備、デザインを簡略化する



これは、大きすぎない家を建てることで、建材や労力、施工時間などの工事費用を削減することができるためです。
例えば、広さを減らすことで、建材の量を減らすことができ、建材費用を削減することができます。
また、広さを減らすことで、労力や施工時間を減らすことができ、労力費や施工費を削減することができます。
それに加えて、広すぎない家を建てることで、家のメンテナンスや清掃のコストも削減できます。
ただし、広さを削減することで、家族や友人などが訪れる際に困るようなスペース不足にならないように、必要なスペースだけに絞り込んだ上で、広さを削減することが重要です。
4-②.不要な高額な設備やデザインを省略する



これは、設備が多いほど、設備費用や取り付け工事費が増えるためです。
例えば、高級なキッチンアイテムやバスルームの設備を減らすことで、設備費用を削減することができます。また、必要最低限の設備だけを設置することで、取り付け工事費を減らすことができます。
ただし、必要な設備だけに絞り込んだ上で、設備を減らすことが重要です。
例えば、住人の暮らしに必要な設備や、将来的に必要になる可能性のある設備は残しておくことが重要です。
4-③.土地代や税金を最小限に抑える



土地代を最小限に抑えるためには、土地を購入する際に、土地価格が高い地域や、開発が進んでいる地域を避け、土地価格が安い地域や、開発が進んでいない地域を選択することが有効です。
また、税金を最小限に抑えるためには、建築許可申請時に、住宅用途地や新築住宅に対する税金の優遇措置を受けることができます。
ただし、土地の購入価格や税金の種類や税率は地域によって異なるため、詳細には地元の市町村に確認した上で決定することが重要です。
>>注文住宅の費用を抑えるポイント10選!注意する点と筆者のコストダウン方法も紹介
5.注文住宅のおすすめの間取り9選!



そこでこの章では、注文住宅で人気の間取りを9つご紹介します。
それぞれの間取りの特徴やメリット、デメリットを解説しながら、あなたにぴったりの間取りを見つけるヒントをお伝えします。
5-①. リビングダイニングキッチン(LDK)と和室の一体型



リビングダイニングキッチン(LDK)と和室の一体型の間取りは、最近人気が高まっている住まいのスタイルです。
メリットとしては、広々とした空間が作れることです。
LDKと和室がつながっているので、壁やドアがなく、開放感があります。家族や友人とのコミュニケーションもしやすくなります。
また、和室の畳がリビングの一部になります。
畳は、座ったり寝転んだりするのに快適で、季節によって温度や湿度を調節してくれます。
また、和室は客間や寝室としても使えるので、多目的に活用できます。
LDKと和室の境界を自由に変えられるのもメリットです。
間仕切りや引き戸などを使えば、LDKと和室の間に仕切りを作ったり、開けたりできます。用途や気分に合わせて、空間を変化させられますよ。
デメリットとしては、防音性が低いことです。
LDKと和室がつながっているので、音が響きやすくなります。
テレビや音楽、会話などの音が和室まで聞こえてしまうことがあるので、プライバシーを重視する人には不向きかもしれません。
また、LDKと和室の調和が難しいこともデメリットです。
LDKと和室は、異なる雰囲気を持っています。
LDKは洋風でモダンな感じですが、和室は和風で伝統的な感じです。
この二つの空間を上手に組み合わせるには、インテリアや色使いなどに工夫が必要です。
5-②. 寝室とウォークインクローゼットのセット



メリットとしては、寝室に直接ウォークインクローゼットがつながっているので、服や小物を収納するスペースに困りません。また、朝の支度も楽になります。
ウォークインクローゼットは、寝室とは別の空間として使えるので、プライベートな時間を過ごすことができます。
例えば、趣味のものやコレクションを飾ったり、読書やリラックスしたりすることができます。
また、ウォークインクローゼットは、寝室から見えないように扉やカーテンで仕切ることができるので、寝室の雰囲気を損なわずにすみます。
デメリットとしては、寝室とウォークインクローゼットのセットの間取りは、一般的に広めの部屋が必要になるので、家賃や購入価格が高くなります。
また、ウォークインクローゼットは、寝室から直接アクセスできる分、整理整頓が必要になります。
もし、ウォークインクローゼットが散らかっていたら、寝室にも影響が出てしまいます。
5-③. 吹き抜けと階段収納の組み合わせ



吹き抜けとは、天井まで空間が開放されている部屋のことで、階段収納とは、階段の下や踊り場に収納スペースを設けることです。
メリットとしては、吹き抜けは空間に広がりと明るさをもたらします。
自然光がたっぷり入り、開放感や解放感を感じられます。また、空気の流れも良くなります。
また、階段収納は、有効に活用できるスペースを増やします。
収納力が高く、物の整理や片付けがしやすくなります。また、階段収納に扉や引き出しをつけることで、見た目もすっきりしますよ。
デメリットとしては、吹き抜けは、冬は暖房効率が悪くなります。
熱が上に逃げてしまうため、床近くは寒くなります。
また、夏は冷房効率も悪くなります。空間が広い分、冷やすのに時間と電力がかかります。
ほかにも、階段収納は、掃除が大変になります。
階段の下や踊り場は埃がたまりやすく、定期的に掃除しないと衛生面で問題があります。
また、階段収納に物を詰め込みすぎると、出し入れが面倒になったり、物が落ちてきたりする危険性もあります。
5-④. ロフト付きの子供部屋



メリットとしては、床面積を有効に使えることです。
ロフト付きの子供部屋は、床面積を二つに分けることができます。
例えば、下のスペースは勉強や遊びに使い、上のスペースは寝る場所にするというように、用途に応じて使い分けることができます。
これにより、限られたスペースでも広く感じられるというメリットがあります。
また、子供の好みに合わせられるのも特徴です。
ロフト付きの子供部屋は、上下のスペースをそれぞれ自由にデザインすることができます。
例えば、上のスペースは星空や森林などのテーマにしたり、下のスペースはカラフルな壁紙やカーテンで飾ったりすることができます。
子供の好みや性格に合わせて、オリジナルな空間を作ることができますよ。
デメリットとしては、安全性に注意が必要です。
ロフト付きの子供部屋は、上下のスペースを移動する際に転落や衝突などの事故が起こりやすいです。
特に小さな子供や寝相の悪い子供は注意が必要です。
また、上のスペースは換気や照明が悪くなりやすいです。これらは、子供の健康や安全に影響する可能性があります。
他にも、子供が成長すると使いづらくなります。
ロフト付きの子供部屋は、子供が小さいうちは楽しいと感じられますが、子供が成長すると使いづらくなります。
例えば、上のスペースは天井が低くなり、立ったり座ったりすることができなくなります。
また、下のスペースは勉強や遊びに集中できなくなります。これらは、子供の成長に合わせて間取りを変える必要があるというデメリットがあります。
5-⑤. サンルームやテラスのあるバルコニー



メリットとしては、サンルームやテラスは、日差しや風を楽しめるだけでなく、植物やペットの飼育にも最適です。
また、洗濯物や布団を干すスペースとしても便利です。
一方で、デメリットとしては、サンルームやテラスの設置費用が高いことや、管理や清掃が手間がかかることが挙げられます。
さらに、サンルームやテラスのあるバルコニーは、隣人との距離が近い場合にはプライバシーが気になるかもしれません。
また、冬場は寒くなりやすいので、暖房設備や断熱材が必要になる可能性もあります。
サンルームやテラスのあるバルコニーの間取りは、メリットもデメリットもありますが、自分のライフスタイルや予算に合わせて選ぶことが大切です。
5-⑥. パントリー付きのキッチン



まず、メリットとしては、収納力がアップすることです。
パントリーにはたくさんの棚や引き出しがありますので、食品や調味料はもちろん、食器や調理器具などもすっきりと収納できます。
また、パントリーはキッチンから一歩離れているので、キッチンが狭くならずに済みますし、見た目もすっきりします。
さらに、パントリーは湿度や温度が低く保たれるように設計されていることが多いので、食品の保存にも適しています。
デメリットとしては、コストがかかることです。
パントリー付きのキッチンは一般的なキッチンよりも広さが必要ですし、棚や引き出しも多くなります。
そのため、建築費や設備費が高くなる可能性があります。また、パントリーはキッチンから離れている分、動線が長くなります。
そのため、料理中に何度も行き来する必要があると、手間や時間がかかってしまうかもしれません。
パントリー付きのキッチンは収納力や見た目が良い反面、コストや動線に注意が必要です。
自分のライフスタイルや予算に合わせて、パントリー付きのキッチンを検討してみるのが大切ですよ。
5-⑦. 玄関ホールとシューズクロークのセット



玄関ホールとは、玄関から入ってすぐの広い空間のことで、シューズクロークとは、靴やコートなどを収納する専用のスペースのことです。
メリットとしては、玄関ホールは来客時にも便利で、お客様を迎える場所として使えます。
また、玄関ホールにベンチや鏡などを置けば、外出前の身だしなみチェックや着替えもしやすくなります。
シューズクロークは靴やコートなどをたくさん収納できるので、玄関がすっきりします。また、シューズクロークに換気扇や除湿機などを設置すれば、靴やコートの湿気や臭いも防げます。
デメリットとしては、玄関ホールとシューズクロークのセットは、床面積が多くなるので、建築費用が高くなります。また、掃除や管理も大変になります。
ほかにも、玄関ホールとシューズクロークのセットは、玄関からリビングまでの距離が長くなるので、移動が面倒になります。特に、荷物が多い時や小さな子供がいる時は大変です。
5-⑧. 書斎やワークスペースのあるリビング



引用:リビングに書斎を。ワークスペース自宅レイアウト実例 – arne interior (interior-arne.com)
書斎やワークスペースのある間取りは、仕事とプライベートのバランスをとるのに便利ですが、注意点もあります。
メリットは、仕事と家事の効率化ができます。
リビングで仕事をすることで、家族とのコミュニケーションが取りやすくなります。
また、家事も手が空いたときにすぐにできます。仕事と家事を同時にこなすことで、時間を有効に使えます。
ほかにも、快適な環境で作業ができること。
リビングは家の中でも広くて明るい場所です。窓から自然光が入り、空気も良いです。
また、ソファやテレビなどのリラックスできるアイテムもあります。仕事に疲れたときには、気分転換になります。
デメリットとしては、集中力の低下につながります。
リビングは家族やペットなどの動きが多い場所です。そこで仕事をすると、気が散ってしまうことがあります。
また、テレビや音楽などの音も集中力を妨げる要因になります。仕事に集中するためには、静かで落ち着いた場所が必要です。
ほかにも、境界線の曖昧化してしまうことがあります。
リビングで仕事をすると、仕事とプライベートの境界線が曖昧になってしまいます。
これは、仕事に没頭しすぎて家族との時間を削ってしまったり、逆に家族や趣味に夢中になって仕事を後回しにしてしまったりすることにつながります。
仕事とプライベートのバランスを保つためには、明確なスケジュールやルールを設定することが必要です。
5-⑨. バスルームと洗面所の一体型



引用:洗面所とトイレを一体化するメリット・デメリット|SUVACO(スバコ)
バスルームと洗面所の一体型の間取りは、最近人気が高まっている住宅のスタイルです。
一体型のメリットは、水回りのスペースを節約できることや、お風呂から出た後にすぐに洗面所で身支度ができることなどが挙げられます。
また、一体型は水漏れやカビの発生を防ぐ効果もあります。
しかし、一体型にはデメリットもあります。
例えば、バスルームと洗面所が同じ空間にあると、湿気が多くなりやすく、換気が必要になります。
また、家族が多い場合は、一人がお風呂に入っている間に他の人が洗面所を使えないという不便さもあります。
さらに、一体型はリフォームや修理が難しく、費用も高くなります。
一体型の間取りは、メリットとデメリットをよく比較して、自分のライフスタイルや予算に合わせて選ぶことが大切ですよ。
6.筆者の間取りを公開



間取り別の価格と特徴を見て貰ったところで、筆者自信の間取りも公開しようと思います。
僕自身が間取りを決めるときに悩んだところやポイント、契約してから失敗した間取りのポイントを紹介していきます。
6-①.筆者の間取り



僕の間取りは4LDKになっています。
最初は3LDKなするつもりだったんですが、僕の両親にも相談したときに老後のことも考えた方が良いよと言われたので1階に和室がある間取りにしました。
老後のことは全く分からない状態ですが、もし必要になったときに家の増築の方が値段が高いので今作っておいた方が良いと思ったんですよね。
みなさんも、間取りを決めるときに老後のことまで考えて決めることで、後悔しない間取りをつくることができますよ。
6-②.筆者が間取りを決める際のポイント



ネットで調べていくうちに、必要なことや要らないことを選別していくことで、自分の理想の家を建てることができますよ。
ここでは、僕自身の体験談を元に間取りを決めるポイントを何個か紹介していきます。
6-②-1.正方形の間取りにする






引用:間取りは正方形が正解だった! (chuumonjutaku.com)
間取りを正方形にする理由は、家のデザインをなるべく正方形にしたかったからです。
家を正方形に近いデザインにすることで、建築コストを下げる狙いがありました。
僕自身はタマホームで建てたのですが、なかなか正方形の家というのがなくてかなり間取りに時間を使いました。
6-②-2.老後も暮らせる家にする



間取りを決める際に、親から老後のことも考えた間取りにするように言われたのがきっかけでした。
僕自身、全く老後のことを考えずに今必要な部屋数だけを見て3LDKにしようとしていたんですよね。
親から言われて、最終的に4LDKにしましたが後悔はしていません。
金額的には200~300万円ほどあがってしまったけど、増築するよりかなりコストを抑えることができました。
みなさんも、色々な人の意見を取り入れて考えるのって大事ですよ。
6-②-3.最低でも1部屋6畳以上にする



自分たちがいろいろなハウスメーカーを見て回った時に、実際に住宅の中を見たときに6畳以上じゃないと狭いなという印象をもったのがきっかけでした。
もし、その部屋を子供部屋にするなら机やテレビ、ベッドなどを置くと6畳以下だとかなり狭くて生活しづらいので1部屋6畳以上というのに決めました。
部屋の大きさを決めるのってかなり難しいですよね?
でも、実際に住宅展示場などで何回も将来こういう使い方にしようとイメージすると、このぐらいの広さは欲しいなという思いがでてきます。
6-③.筆者の間取り失敗ポイント



自分の中では、かなり間取りを考えたつもりでも後からこうすればよかったという思いは出てくるんですよね。
実際に家が建って中に入ってみることで、自分の中の失敗ポイントがいくつか見えてきました。
ここでは、実際に家が建った後に感じた筆者の間取り失敗ポイントを紹介していきます。
6-③-1.LDK16畳は少し狭い



でも、実際に家が建つと思った以上に狭くてダイニングテーブルやテレビを置くとかなり圧迫感があります。
土地の関係上仕方なかったのですが、もう少し余裕のあるLDKだと暮らしやすいかなという思いはあります。
もし失敗しても、収納の仕方などを考えたり、テレビは壁掛けなどにすることで空間を広くとることは可能なのです。
6-③-2.家事動線が悪い



これも、家を正方形に近づけるためや水回りは一か所にまとめるのが主流だとハウスメーカーから言われたんですよね。
実際に使うのを想像すると、洗濯物を干すときも行ったり来たりしないといけないのでかなり不便に感じます。
一応和室の部屋に選択を干すための竿を天井から吊り下げるようにしましたが、それでも少し家事動線が悪いかなという印象です。
今だったら、洗濯室に洗濯物をかけれるようにするか、すぐ隣の部屋に干せるような間取りにすると思います。
7.まとめ



今回の記事を読むまでは、自分たちの予算だと、どのくらいの家が建てられるか不安
だったという方も多いのではないでしょうか?
理想の家を建てることができるか不安かもしれませんが、予算と間取りを照らし合わせていきましょう。
この記事を通して、理想の家作りを後押しできれば、幸いです。
\ 間取り、資金計画で悩んでいる方必見!/
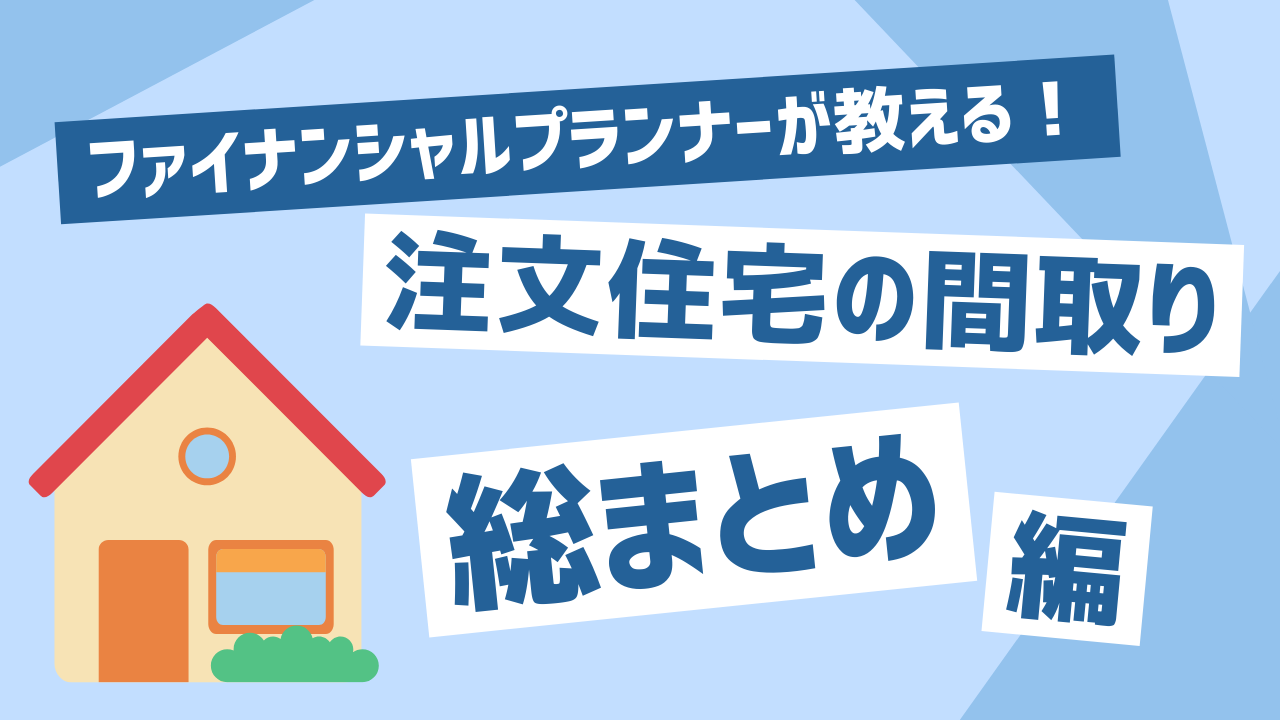


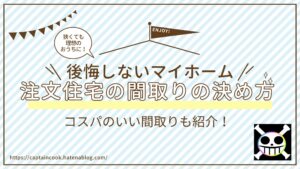
コメント